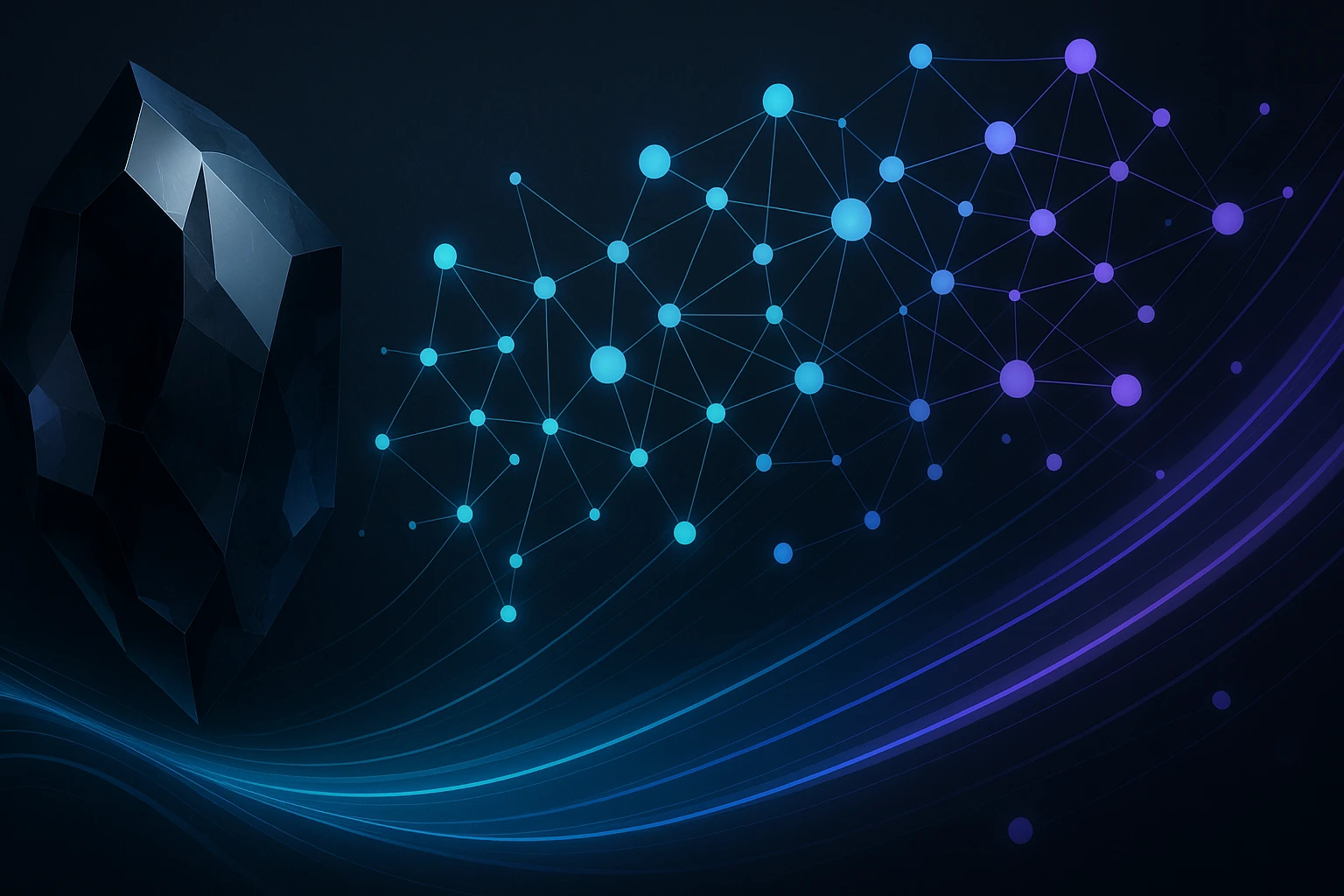ObsidianとAIとの組み合わせを可能とするプラグインや、Obsidianと組み合わせが可能なAIがいろいろ出てきたので、概略ではあるが比較を行ってみた。
比較には、GPT-5とPerplexity Proを使い、まずは、GPT-5に基本的な質問から行い、その後、Perplexity Proにも同様の質問を行った。
(注)本記事の内容は正確性を保証するものではない。
Custom Framesは、AIの画面も表示することができるので比較対象に入れている。
ObsidianとCodex CLIを組み合わせた構成の使い方については、下記の記事で紹介している。
まずは、GPT-5の回答を紹介する。
obsidianとAIを組み合わせる場合、下記の方法があると思いますが、各方法を比較してください。
・Smart Composer
・Obsidian Copilot
・Custom Frames
・Codex CLI+Terminal
・Gemini CLI+Terminal
・Claude CLI+Terminal
GPT-5 の回答
了解です。Obsidian×AIの6方式を、目的別に一気見できる比較表+使い分けの指針でまとめました。
ざっくり結論(用途別の最適)
- ノート内で完結・RAG重視: Smart Composer or Obsidian Copilot(UI統合が強い)
- 外部WebツールをObsidianに埋めたい: Custom Frames(iFrameで何でもパネル化)
- コード生成・修正・テスト実行まで“端末でガンガン回す”:
- Google系で無料枠が太い/ワークスペース連携 → Gemini CLI (Google for Developers, GitHub)
- テスト~PRまでの一連を端末中心で回す → Claude CLI(Claude Code) (Anthropic, Anthropic)
- GPT系エージェントをローカル中心で使う → Codex CLI (GitHub, OpenAI 開発者, OpenAI)
一覧比較
| 項目 | Smart Composer | Obsidian Copilot | Custom Frames | Codex CLI+Terminal | Gemini CLI+Terminal | Claude CLI+Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主目的 | Vault文脈のAI編集/生成 | Vault横断チャット/RAG/エージェント | Webアプリの埋め込み | ローカルで動くGPT系コーディングエージェント | 端末で動くGeminiエージェント(ReAct/MCP) | 端末で動くClaudeのコーディングエージェント |
| Obsidian統合 | プラグインUI/選択範囲編集/文脈タグ | プラグインUI/ノート検索/外部ソース連携 | iFrameパネル化(UI統合は最小限) | 直接統合なし(コマンド/スクリプトで橋渡し) | 直接統合なし(同左) | 直接統合なし(同左) |
| RAG(Vault参照) | あり(ファイル/フォルダを文脈指定) (GitHub, Obsidian Forum, Obsidian Stats) | あり(Vault検索・要約・エージェント) (Copilot for Obsidian, GitHub, Obsidian) | なし(埋め込む先次第) (GitHub, Obsidian, Obsidian Stats) | なし(自作でRAG可) (GitHub) | MCP/ツール連携で柔軟(RAGは自作) (Google for Developers, Google Cloud) | ワークフロー連携強(RAGは自作) (Anthropic, Anthropic) |
| エージェント/ツール実行 | 軽エージェント (編集適用) | エージェント機能 (拡張中) | なし (表示枠) | ローカル実行・編集・テスト/実行 | ReActループ+MCPで実行系が強い | Issue→PRまで含む実務フロー |
| 学習コスト | 低~中 | 低~中 | 低 | 中 | 中 | 中 |
| セットアップ難度 | 低(コミュニティ/BRAT経由も) (Obsidian Forum) | 低(公式サイト/コミュニティ配布) (Copilot for Obsidian, Obsidian) | 低(プラグイン導入→URL指定) (GitHub) | 中(npm/brew+権限) (GitHub) | 中(npm/brew+API設定) (GitHub, Google Cloud) | 中(インストール+設定) (Anthropic) |
| コスト感 | モデル次第 | モデル/プラン次第 | 無料(埋め先次第) | ChatGPT系プラン/トークン | 無料枠が太い+API連携可(※仕様上) (Google for Developers) | プラン/トークン |
| 向く作業 | ノート整形/要約/執筆支援 | 情報探索~要約~生成の一体化 | YouTube/Drive/Appsを隣に置く | 既存Repoの改修・検証 | バグ修正/新機能/テスト強化 | 課題→修正→テスト→PRまで |
各方式のポイント(短評)
Smart Composer
- 強み: ノートに“貼り付いたまま”文脈指定→提案→その場で編集適用。Vault参照の粒度が細かい。(GitHub, Obsidian Forum)
- 弱み: 本格的な自動実行や外部ツール連携は限定的。大規模自動化は別途。(GitHub)
Obsidian Copilot
- 強み: Vault横断チャット、要約、外部ソース(Web/YouTube等)にも触る“総合アシスタント”。学習コストが低い。(Copilot for Obsidian, GitHub)
- 弱み: 実コードの実行・テストの自動化はターミナル系ほどは踏み込めない。(Copilot for Obsidian)
Custom Frames
- 強み: ほぼ任意のWebアプリをパネルとしてObsidianに“住ませる”。ワークフローを一画面に集約。(GitHub, Obsidian)
- 弱み: AI自体は“埋めた先”任せ。RAGや編集適用は別ツールで。(GitHub)
Codex CLI+Terminal
- 強み: ローカルでコードを読み/変更/実行しながら進める“作業エージェント”。GPT-5推奨。(GitHub, OpenAI 開発者, OpenAI)
- 弱み: Obsidianとの橋渡しは自作(スクリプト/CLI呼び出し)。UI統合はない。(GitHub)
Gemini CLI+Terminal
- 強み: ReActループ+MCPサーバー連携で、テスト/修正/ツール呼び出しの自動化がしやすい。Google公式ドキュメント&GitHubで整備。(Google for Developers, GitHub)
- 弱み: Obsidianと直結UIはなし(スクリプト連携で補う)。(Google for Developers)
Claude CLI(Claude Code)+Terminal
- 強み: 端末中心でIssue→コード→テスト→PRまでの実務フローを一貫支援。ドキュメントが充実。(Anthropic, Anthropic)
- 弱み: こちらもObsidianとは直接UI統合なし。(Anthropic)
Obsidian中心ワークフローでの“賢い組み合わせ”
- ノート作成~整理: Smart Composer(微修正や要約)→ Obsidian Copilot(横断検索・要約・下書き生成)
- 開発系の重作業(リポジトリ修正・テスト・PR):
- Obsidianで要件/仕様をまとめる → Gemini CLI or Claude CLI or Codex CLIで実作業
- 結果ログはCLI側からMarkdown出力→Obsidianに保存(シェルスクリプト/自動保存)
- 外部情報の横目確認: Custom Framesでドキュメントビューア/CIダッシュボード/YouTubeなどをサイドパネル化
最小構成の導入順(地方都市の回線事情でも軽い順)
- Custom Frames:まず“作業一画面化”。(GitHub)
- Smart Composer:ノート内RAG&編集適用で日常快適化。(GitHub)
- Obsidian Copilot:Vault横断チャットと要約で“探す→纏める”を短縮。(Copilot for Obsidian)
- (必要に応じて)CLI系:
- Google生態系と無料枠重視 → Gemini CLI (Google for Developers)
- PR駆動の強い開発フロー → Claude CLI (Anthropic)
- GPT系をローカルで使い倒す → Codex CLI (GitHub)
各方式の無料枠について教えてください。
GPT-5 の回答
了解です。各方式の「無料枠(= 追加課金なしでどこまで使えるか)」を一望できるようにまとめました。
まとめ(無料枠)
| 方式 | 無料枠の有無 / 中身 | 備考 |
|---|---|---|
| Smart Composer(Obsidianプラグイン) | プラグイン自体は無料(オープンソース)。モデル利用は自前のAPIキーやローカルLLMに依存(=プロバイダの課金/無料枠を消費)。 | 公式リポジトリに有料プランは記載なし。使うモデル側の枠(OpenAI/Anthropic/Google等)を消費します。 (GitHub) |
| Obsidian Copilot | Freeプランあり($0):FOSS機能+BYO API(PDFなど一部制限、AIエージェント等は不可)。 | 上位のPlus(月額)で上限解放・機能拡張。無料枠の範囲は公式価格ページが明示。 (Copilot for Obsidian) |
| Custom Frames(Obsidianプラグイン) | 無料(オープンソース)。 | これは“Webアプリを埋め込む”プラグインで、AI利用の課金は埋め込み先(例:ChatGPT Web等)に依存。(GitHub) |
| Codex CLI+Terminal(OpenAI) | Codex自体はOSS/無料で入手可だが、利用はChatGPTの有料プラン(Plus/Pro/Team/Edu/Enterprise)に含まれる=実質「ChatGPTのサブスク内の枠」を消費。 | OpenAIヘルプに“CodexはChatGPTプランに含まれる/プラン別の使用上限あり”と明記。無料プランでのCodex利用は案内なし。 (OpenAI Help Center, OpenAI 開発者) |
| Gemini CLI+Terminal(Google) | 個人Googleアカウントに紐づく “無料ライセンス(Gemini Code Assist)” で利用可。上限は60リクエスト/分・1,000/日。 | 公式発表に上記の数値が明記。APIの一般レート制限ドキュメントも併記。(blog.google, Google AI for Developers) |
| Claude CLI(Claude Code)+Terminal(Anthropic) | 無料プランは“Claude(チャット)”の体験枠のみで小さめ。Claude Code を本格利用するにはサブスク(Pro/月$17-20、Max/月$100/200)が必要=サブスク内の使用上限を消費。 | 価格ページ/Claude Codeページにプランと包含関係が記載。詳細なメッセージ上限は“5時間あたりの目安”として案内される場合あり。 (Anthropic) |
補足メモ
- Obsidian系プラグイン(Smart Composer / Copilot / Custom Frames)は、基本ソフトやプラグイン自体は無料。ただしAIの推論コストは“使うモデル側”を消費します(OpenAI/Anthropic/GoogleのAPIや、ローカルLLMはPC資源)。(GitHub, Copilot for Obsidian)
- Codex / Claude Code / Gemini CLIのようなCLI系“作業エージェント”は、ベースのツールは無料入手でも、実使用は各社のサブスクや無料ライセンスの上限に従うのが実情です。特にGemini CLIは個人向け無料枠が太い(60rpm/1000rpd)。
CodexはChatGPTサブスクに含まれる、Claude CodeはPro/Maxサブスクが前提という位置づけです。
(blog.google, OpenAI Help Center, Anthropic)
地方都市でのご利用前提でも、まずはGemini CLIの無料枠でワークフローを試し(Obsidian側はSmart Composer/CopilotはBYO APIで最小構成)、必要に応じてCodex or Claude Codeを追加、がコスト効率は良いと思います。
Obsidian Copilotの「Vault横断チャット」も気になるが、Smart Composer、Codex CLI+Terminal、Gemini CLI+Terminalで各エージェントの使い勝手を確認したい。
次は、情報源の活用について試行した内容を紹介する。
紹介するのは、1つのチャット内で、複数回、一連の質疑応答を行い、それらの質疑応答の回答に利用した情報源をまとめて活用を図るものである。
このチャットで使った情報源の情報源集を作ってください。
その際、各情報源の内容に関する簡単な説明文を付けてください。
GPT-5 の回答
了解です。公式ドキュメントや配布元を中心に、今回の話題(6方式)に直結する情報源集をまとめました。各項目に“何が分かるか”の短い説明も付けています。
情報源集(一次情報中心)
Obsidian系プラグイン
- Smart Composer(GitHub) — プラグイン本体。Vault参照しながらAIで執筆・編集する趣旨、導入法、機能概要。 (GitHub)
- Smart Composer(Wiki) — 使い方やコンセプトの補足ドキュメント。 (GitHub)
- Custom Frames(GitHub) — 任意WebアプリをObsidianのペインに埋め込むプラグイン。サンプル・設定例あり。 (GitHub)
- Custom Frames(Obsidian Hub) — 公式ハブでの概要紹介(機能の要点を手早く確認)。 (Obsidian)
- Obsidian Copilot(公式サイト) — 機能の全体像(ノート横断チャット、要約、エージェント等)。 (Copilot for Obsidian)
- Obsidian Copilot(Pricing) — Free/Plusの範囲や“BYO API”など、無料枠の条件確認に最適。 (Copilot for Obsidian)
- Obsidianプラグイン一覧(Copilot) — Obsidian公式のプラグイン検索結果(掲載の正式名称や説明を確認)。 (Obsidian)
CLI/エージェント(Google / OpenAI / Anthropic)
- Gemini CLI(Google 公式ブログ) — 無料枠(最大60リクエスト/分・1,000/日)や全体像、ユースケースを公式発表で確認。 (blog.google)
- Gemini CLI(Developers Blog: VS Code統合) — VS Codeの“ネイティブ差分”など、実務での使い勝手の最新アップデート。 (Google Developers Blog)
- Gemini CLI(GitHub) — リポジトリ本体。セットアップ、MCPサーバー連携、上限に触れる記述もあり。 (GitHub)
- Codex CLI(OpenAI 開発者サイト) — Codex CLIの公式解説。ローカルでのコードの読み書き・実行を含む基本機能と導入。 (OpenAI 開発者)
- Codex CLI(GitHub リポジトリ) — インストール手順(npm/brew)や更新状況、ライセンス等の一次情報。 (GitHub)
- Claude Code(Overview) — 端末常駐の“エージェント的”開発ツールとしての位置づけ・できることの俯瞰。 (Anthropic)
- Claude Code(CLIリファレンス) — コマンド/フラグ、設定(モデル・メモリ・フック等)を詳細に確認可能。 (Anthropic)
参考(ニュース・解説)
- Gemini CLI(9to5Google) — 無料枠や文脈長など、公式発表を噛み砕いた技術メディアの要約。 (9to5Google)
- Codexアップデート(ITPro) — Codexの最近の機能拡張・利用形態(IDE/端末/ウェブ連携など)の概況。 (IT Pro)
情報源の公開日や更新日を含めたタイムラインを作ってもらえますか
GPT-5 の回答
了解です。今回の比較・無料枠説明で参照した主な一次情報を、公開日(または更新日)順にタイムライン化しました
(時刻はJST基準ではなく各サイト表記のままです)。
情報源タイムライン
- 2024-10-17|Smart Composer 公開告知(Obsidian公式フォーラム)
Obsidian向けAIプラグイン「Smart Composer」の機能概要(文脈指定チャット、編集適用、Vault検索RAGなど)の初期案内。 (Obsidian Forum) - 2025-02-24|Anthropic「Claude 3.7 Sonnet と Claude Code」発表
Claude Code(ターミナル常駐の“エージェント的”開発ツール)に関する公式告知群の中で、機能拡張の位置づけが示される。 (Anthropic) - 2025-05-07|Latent Space「Claude Code」特集(開発チーム出演)
Claude Codeの狙い・設計思想・使い方を関係者が詳述。一次情報に近いインタビュー的まとめ。 (Latent.Space) - 2025-05-16|OpenAI「Codex(開発者エージェント)研究プレビュー」発表
Codexの並列タスク処理・PR提案など“エージェント”としての基本像を公式が提示。のちのCodex CLI/IDE連携の前提となるアナウンス。 (OpenAI) - 2025-06-25|Google 公式ブログ「Gemini CLI: your open-source AI agent」
端末向けオープンソースAIエージェント「Gemini CLI」を発表(無料枠や能力の概観)。同日付の複数メディア/まとめ記事も相次ぐ。 (blog.google, The Economic Times, The Verge) - 2025-06(リポジトリ開設・初期ドキュメント)|Gemini CLI GitHub
無料枠(個人Googleアカウントで60 req/min・1,000 req/day)やVS Code連携、MCP対応、リリース運用方針(Weekly/Preview/Nightly)などがREADMEに明記。 (GitHub) - 2025-07-23(ページ登録日)|Obsidian Copilot 解説ページ(サードパーティ)
Obsidian Copilotの機能概要を俯瞰できる紹介記事(後日更新あり)。 (Jimmy Song) - 2025-08-05|Anthropic「Claude Opus 4.1」発表(Claude Codeでも提供)
Claude Codeで利用できるモデル強化の節目。Claude Codeの提供状況にも言及。 (Anthropic) - 2025-08-13|Google Developers Blog「Gemini CLI + VS Code」大型アップデート
“ネイティブ差分”“文脈連携”など、VS Code統合の深化を告知。実運用での作業効率を大きく改善する内容。 (Google Developers Blog) - 2025-08(不定期)|Obsidian Copilot リリース(GitHub Releases)
v3準備中のアナウンスや直近の暫定リリース(GPT-5対応)など、最新の変更履歴が確認できる。時系列確認に有用。 (GitHub) - (随時更新)|Smart Composer GitHub
READMEに機能詳細・MCP対応などの更新が随時反映。最新版の機能把握はここが最短。 (GitHub) - (日付情報なし/常設)|Custom Frames
GitHubおよびObsidian Hubのプラグインページ。iFrameでWebアプリをペイン化する基本と設定例を恒常的に参照可能。 (GitHub, Obsidian)
参考(二次情報):Gemini CLIの無料枠や機能をまとめた技術メディア記事・ニュース(理解の補助用)
9to5Google/IndiaTimes/The Verge 等(2025年6月報道)。 (Indiatimes, The Verge)
必要でしたら、このタイムラインをObsidian向けのMarkdown(内部リンク・タグ付き)や、日付ソート済みのCSVにしてお渡しします。
AIの画面に表示されている情報を、obsidianの文書にコピペする作業について、各方式を比較してください。メリット・デメリットという項目も追加してください。
GPT-5 の回答
了解です。目的が「AIの画面に出た内容をObsidianの文書へコピペする」ことに絞られるので、**“どれが最短でキレイに貼れるか/再現性が高いか”**を軸に6方式を比較します。
ざっくり結論
- 最短でキレイに貼る:Obsidian Copilot(ノート直書き/追記が容易) or Smart Composer(選択範囲に直接反映)
- 画面を見ながら必要部分だけ抜く:Custom Frames(同一画面でコピペ、視線移動が少ない)
- コピペ自体を“やめて”Markdownを直接生成:CLI系(Codex/Gemini/Claude)でmd出力→Vaultへ保存が最も再現性・履歴管理に強い
比較表(“コピペ作業”に特化)
| 項目\方式 | Smart Composer | Obsidian Copilot | Custom Frames | Codex CLI+Terminal | Gemini CLI+Terminal | Claude CLI(Claude Code)+Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨キャプチャ手段 | macOS標準(⌘⇧4/5、クリップボード直貼り可) | 同左 | 同左(埋め込み画面を見ながら) | screencaptureで所定パス保存 | 同左 | 同左 |
| Obsidianへの貼付動線 | ノートへドラッグ/⌘V→その場で整形 | 回答横で貼付→追記生成 | 同一画面で選択→ドラッグ/⌘V | md自動生成で![[画像]]挿入(コピペ不要) | 同左 | 同左 |
| 画像ファイル管理(保存/命名) | 添付先サブフォルダへ自動格納(設定推奨)/命名は手動運用 | 同左 | 同左 | 日付スラグ+連番など強制命名可 | 同左 | 同左 |
| キャプション/メタ付与 | プロンプトで説明文生成→直下に追記 | 質問/回答/時刻テンプレ流用しやすい | ノート側テンプレで手動付与 | ヘッダーにsource/日時/操作を自動記載 | MCP/関数で自動生成容易 | Issue/PRログとメタ連携しやすい |
| 自動化のしやすさ | 中(スニペット/テンプレ) | 中 | 低~中 | 高(ラッパー/フック/Git) | 最高(取得→要約→保存を一括) | 高 |
| 想定トラブル | 連続貼付でノート肥大・画像名が散る | スレッド肥大で見通し低下 | 埋め込みWebのコピー挙動が変化 | 初期セットアップ学習コスト | 鍵/環境設定 | プラン上限 |
| メリット | 貼る→説明が一画面で完結 | 思考ログ化が速い | 視線移動最小・選択精度高 | 再現性&資産化最強 | 無料枠太め+自動化最適 | 開発ログ一体化に強い |
| デメリット | 命名統一は手動になりがち | 画像整理は設定頼み | RAG/説明は他手段依存 | 単発スクショは準備が重い | 単発用途に過剰 | 単発用途に過剰 |
実務TIPS(“貼るのが速く、後で見返しやすい”ために)
- 貼付テンプレを1つ決めて固定化
- 例)YAML+本文:
--- source: "" # URL or アプリ名 captured_at: "" # 2025-09-06T12:34+09:00 prompt: "" # 任意 model: "" # 使ったモデル ---その下に本文をMarkdownで。コードは必ず“`lang で囲む。
- 例)YAML+本文:
- 画像は“必ずファイル保存→相対リンク”
- 画像は
/assets/ai/<YYYY>/<MM>/に保存し、![[ファイル名]](Obsidian形式)で参照。 - Web UIのコピーで画像が消えるのを防ぎ、再現性を担保。
- 画像は
- CLI系は“コピペをやめる”のが正解
run_ai.shのようなラッパーを用意:- 入力(URL/選択テキスト/プロンプト)→
- AI出力(md)→
- テンプレヘッダー自動付与→
icloud_vault/Clippings/AI/に日付Slugで自動保存。
- これで貼るという作業自体が不要になり、履歴管理と検索性が向上。
- Custom Framesは“視線移動最小化+選択精度向上”
- 重要見出しだけ選択→貼付→Smart Composerで整形が速い。
- 余計なUI要素まで混ざったら、**ペースト直後に
⌘Z→⌘Shift+V(プレーン貼付)**で整える。
どれを選ぶ?(用途別おすすめ)
- “見ながらちょっとだけ抜きたい”:Custom Frames+Smart Composer
→ 同画面で選択→貼付→その場整形。小回り最強。 - “毎回同じ形式で残したい(あとで検索・再利用)”:CLI系(Gemini/Claude/Codex)
→ md直出力・自動保存で“貼る”をやめる。 - “ノートにどんどん追記していく”:Obsidian Copilot
→ ノートへ送る→追記→要約のループが短い。
各方式でのコピペ作業を比較したが、定番の、選択範囲を新規ノートに抽出/既存ノートに追記できるプラグイン「 Note Refactor」や、Webページ全体を取り込めるChrome拡張機能「Obsidian Web Clipper」を使うのがよさそうだ。
以下、同様の質問をPerplexity Proに対して行った結果を紹介する。
obsidianとAIを組み合わせる場合、下記の方法があると思いますが、各方法を比較してください。
・Smart Composer
・Obsidian Copilot
・Custom Frames
・Codex CLI+Terminal
・Gemini CLI+Terminal
・Claude CLI+Terminal
Perplexity Pro の回答
ObsidianとAIを組み合わせる際の主要な方法(Smart Composer・Obsidian Copilot・Custom Frames・Codex CLI+Terminal・Gemini CLI+Terminal・Claude CLI+Terminal)は、それぞれ特長や適用範囲が異なります。以下に各手法の特徴と比較をまとめます。note
比較表
| 方法 | 操作性 | 対応AI/モデル | Obsidianとの統合度 | コスト管理 | カスタマイズ性 | プライバシー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Composer | クリック/右ペイン式UI | GPT, Gemini, Claude他 | Markdown編集と並列 | API自己管理 | モデル切替/独自プロンプト | 高 |
| Obsidian Copilot | サイドパネル/チャットUI | 各種LLM(GPT, Gemini他) | ノート要約/QA/翻訳/チャット | API自己管理 | カスタムプロンプト, 拡張 | 高 |
| Custom Frames | iFrameでWeb埋込 | Webサービス全般 | Obsidian内マルチ窓 | 不要 | 任意Web/表示カスタム | 埋込依存 |
| Codex CLI+Terminal | コマンドライン | OpenAI Codex | Obsidian内(Terminal要) | API自己管理 | 設定次第で柔軟 | 高 |
| Gemini CLI+Terminal | コマンドライン | Gemini | Obsidian内(Terminal要) | 一部無料 | コマンド自作・応用可能 | 高 |
| Claude CLI+Terminal | コマンドライン | Claude Code | Obsidian内(Terminal要) | API自己管理 | CLI設計次第で拡張大 | 高 |
各方式の詳細
Smart Composer
- 主にMarkdown編集をAIで支援(要約/リライト/発想展開等)し、ワンクリックでAI提案を適用できる。note
- OpenAI, Gemini, ClaudeなどAPIを自己管理で複数モデル切替可。uhd-inc
- ローカル保存が前提でプライバシー重視。ノートリンク構造(Zettelkasten)も生かせる。uhd-inc
Obsidian Copilot
- ノート内容把握を重視し「第二の脳」的な知的支援を提供。メモ要約、QA、翻訳、コマンド実行など機能が多彩。namaraii
- 複数LLMを切替可能、ローカルインデックスでVault内容そのものをAIに参照・活用できる。qiita
- ベクトルDBでプライバシー配慮しつつ、高度なカスタマイズ対応。namaraii
Custom Frames
- 任意のWebサービス・AIチャット画面(例: ChatGPT, Notion等)をiFrameでObsidian内に埋め込む。minatokobe
- Obsidianとの直接的な連携はないが、マルチタスク画面で作業効率を大幅補強できる。minatokobe
- 埋め込んだWebアプリの機能拡張や見た目カスタムも柔軟。note
Codex CLI+Terminal
- OpenAI CodexコマンドラインツールをObsidianのターミナルプラグイン経由で活用。github
- プロンプトに応じてコーディング/自動化指示が高精度。細かなカスタマイズや自動化タスクにも強い。note
- 課金はAPI自己管理式、CLIが基本のためエンジニアリング用途に最適。github
Gemini CLI+Terminal
- Google GeminiのAI CLIを同様にObsidian内で利用。izanami
- 無料枠で始められ、小回りが効く。要約・執筆・自動変換など高速作業に便利。nounai-librarian
- ターミナルに抵抗がなければ一画面で完結。nounai-librarian
Claude CLI+Terminal
- Anthropic ClaudeのCLIをターミナルから実行、Obsidianのノート編集と連携。note
- コマンドカスタマイズで、特に自然言語処理や長文要約を得意とする。zenn
- 専用コマンドやホットキー設定も柔軟。note
選び方のポイント
- ノート中心の編集支援やAI文章校正が主な目的なら「Smart Composer」「Copilot」が最適。qiita
- 多彩なWebサービス併用や、視認性・作業性を重視するなら「Custom Frames」。note
- エンジニアリングや自動化・生成AI操作を自在に使いたい場合はCLI(Codex, Gemini, Claude+Terminal)の導入価値が高い。zenn
機能や導入難易度、コスト、カスタマイズ可能範囲、セキュリティ重視度などの観点から、自身の用途や運用方針に最適な組み合わせを検討するのが良いでしょう。uhd-inc
Codex CLI+Terminalの場合、API使用料を発生させないで使う方法はないのですか。
Perplexity Pro の回答
Codex CLI+Terminalは、API使用料を発生させずに利用する方法がいくつかあります。主な手段は以下の2つです。nikkeimatome
1. サブスクリプション連携(ChatGPTプラン)
- ChatGPT Plus、Pro、Teamプランユーザーは、「Sign in with ChatGPT」機能を使うことで、追加API課金なしでCodex CLIを利用できます。note
- この場合はAPIキーの設定が不要で、月額固定料金(例:Plusなら月額20ドル)のみで利用可能です。
- 導入はCLI最新版をインストール後、
codex --freeコマンドや「Sign in with ChatGPT」オプションからアカウント認証を行います。ar-aca
2. ローカルLLM連携(OllamaやLM Studio等)
- Codex CLIをローカルで動作する大規模言語モデル(LLM)と組み合わせることで、インターネットを介さずAPI料金も不要な環境が構築できます。taneyats
- 例:Ollama(オープンソースモデル管理ツール)やLM Studioで「qwen-4b」等の完全無料ローカルモデルを用意し、Codex CLIの設定ファイル(config.toml)を編集して指定します。classmethod
- この方法なら一切の課金無しでCLIの生成やコマンド実行を実現しますが、モデル性能・日本語対応状況はクラウドモデルに劣る場合があります。
3. Gemini無料枠連携
- Codex CLIはGoogle Geminiの無料API枠とも連携できます。Gemini APIの無料割当内であれば、API料金は発生しません。qiita
これらにより、API従量課金を避けてCodex CLIを活用することが可能です。用途・作業負荷・プライバシー要件などに応じて選択してください。nikkeimatome
OllamaなどローカルLLMでCodex CLIをAPIキー不要で動かす設定はどう違うのですか
Perplexity Pro の回答
Codex CLIをOllama等のローカルLLMでAPIキー不要に動かす際の設定は、設定ファイル(config.toml)のプロファイル・プロバイダ記述を「OpenAI API」から「Ollama」(または「LM Studio」)へ切り替えることが最大の違いです。taneyats+3
設定の主な違い
必須作業
- OllamaやLM StudioなどローカルLLMのインストール・起動(例:
ollama serve、lms server start)。aries67 - 利用したいモデル(例:qwen-4b, gpt-oss-20b)の事前ダウンロード。taneyats
config.toml 記述例
- Ollamaの場合(
~/.codex/config.toml): text[model_providers.ollama] name = "Ollama" base_url = "http://127.0.0.1:11434/v1"
[profiles.qwen4b-ollama]
model_provider = “ollama” model = “qwen:4b”
base_urlをOllamaのAPIエンドポイント(デフォルト: 11434)に設定。noteprofileで利用モデルを指定し、CLI実行時にcodex --profile qwen4b-ollama等で切り替え。dev
LM Studioの場合(例:gpt-oss-20b):
text[model_providers.lmstudio]
name = "LM Studio"
base_url = "http://localhost:1234/v1"
[profiles.gpt-oss-20b-lms]
model_provider = “lmstudio” model = “gpt-oss:20b”
- LM StudioのAPIエンドポイント(デフォルト: 1234)を指定。note
APIキー不要
その他の注意点
まとめると「プロバイダー記述」と「APIエンドポイント」、「model_provider」「model」の指定をローカルLLM用に変更するのが主な違いで、APIキーが一切不要になる点がポイントです。dev
このチャットで使った情報源の情報源集を作ってください。
その際、各情報源の内容に関する簡単な説明文を付けてください。
Perplexity Pro の回答
以下は、このチャットで使用した主な情報源(ウェブページ)とそれぞれの内容についての簡単な説明です。
情報源リストと説明
1. ObsidianをCursorぽく使う。AI導入プラグイン「Smart Composer」note
- Smart Composerの機能やインストール手順、使い方、複数AIモデル(GPT/Gemini/Claude等)への対応例、メリット(ノート編集支援・ローカル実行)などについて実践的に解説したブログ記事です。
2. 【Obsidian】上で生成AIを使えるPlugIn【Smart Composer】使ってみたuhd-inc
- Smart Composerの操作性・AI切り替え方法・導入初期設定・プライバシー観点や利点など、具体的な活用ポイントを紹介する解説記事です。
3. Obsidian Copilotプラグイン – namaraii.comnamaraii
- Obsidian Copilotの概要、FAQ、基本機能(ノート要約・QA検索・第二の脳的運用)や導入手順が記されています。
4. Obsidian Copilotのすゝめ:ノート活動を変えるかもしれない壁打ちAIqiita
- Copilot導入の背景、特性(ベクトルDB活用の優位性・ノートへの深い統合)、実用例がユーザー目線でまとめられています。
5. Ollamaと連携してOpenAI Codex CLIをローカルで試すtaneyats
- Codex CLIをOllamaと連携してAPIキー不要・無料で使うための実践的な設定方法、config.tomlの具体例、動作検証内容が詳細に記載されています。
6. オフラインでも使える!OpenAI Codex CLI + LM Studio でローカル…classmethod
- Codex CLIとLM StudioなどローカルLLMをAPI不要で連携するための手順や、実際の運用イメージ・メリット・注意点を詳しくまとめた記事です。
7. 【Codex CLI】GPT-5をChatGPTサブスクで定額利用・APIキー不要…nikkeimatome
- Codex CLIがAPIキー無し・ChatGPTサブスク(Plus/Pro/Team)認証でAPI従量課金なしに利用可能な方法や、そのステップを解説しています。
8. Codex CLI がAPIキー不要で利用可能になったので設定方法を解説!ar-aca
- APIキーなし(あるいはChatGPTサブスク連携のみ)でCodex CLIを動かすための具体的な新機能や設定変更点を詳細に記載した新着解説記事です。
9. 【最新アプデ】OpenAI Codex CLI 徹底解説!ChatGPTのプランで…note
- Codex CLIのAPI利用形態の比較やChatGPTサブスクでの無料運用、各種プロファイル切り替え・設定例を図解で示す記事です。
10. Codex CLI: Running GPT-OSS and Local Coding Models…dev
- Codex CLIがローカルLLM(Ollama, LM Studio, MLX等)と連携できるようになった際の設定方法、エンドポイント指定やconfig.tomlのサンプル、CLI運用アイデアが実例付きで説明されています。
11. ローカルLLMで“Codexごっこ”してみた — LM Studio × gpt-oss…aries67
- LM Studioと組み合わせてCodex CLIをローカル運用する際のstep-by-stepガイド、各種モデル対応状況、パフォーマンス備考がまとまった解説です。
12. 【Ollama】Codex CLIでgpt-oss:20bを動かす!コンテキストサイズ…taneyats
- Codex CLI×Ollama環境での大規模LLMモデル対応や細かなカスタマイズ(コンテキストサイズ・先読み設定等)事例と注意点についても記載されています。
これらの情報源を通じ、各種AIツールとObsidianとの連携方法・運用のコツ・APIキー不要運用(ローカルLLM活用やChatGPTサブスク連携)の最新動向・実践手順などを詳細に比較・説明しました。
情報源の公開日や更新日を含めたタイムラインを作ってもらえますか
Perplexity Pro の回答
以下は、各情報源の公開日(または更新日)と内容を時系列で整理したタイムラインです。
| 公開日 | 情報源タイトル |
|---|---|
| 2025-02-26 | Obsidian Copilotプラグイン – namaraii.com Copilotプラグインの概要・導入と機能解説namaraii |
| 2025-03-15 | Obsidian Copilotのすゝめ:ノート活動を変えるかもしれない壁打ちAI Copilotの応用事例・活用法qiita |
| 2025-06-02 | ObsidianをCursorぽく使う。AI導入プラグイン「Smart Composer」 Smart Composerの使い方・利点解説note |
| 2025-08-07 | Codex CLI がAPIキー不要で利用可能になったので設定方法を解説! API不要導入方法・新機能紹介ar-aca |
| 2025-08-08 | 【Codex CLI】GPT-5をChatGPTサブスクで定額利用・APIキー不要… API課金なし活用ノウハウnikkeimatome |
| 2025-08-08 | 【最新アプデ】OpenAI Codex CLI 徹底解説!ChatGPTのプランで… 設定例・運用ポイントnote |
| 2025-08-17 | ローカルLLMで“Codexごっこ”してみた — LM Studio × gpt-oss… LM Studio運用手順と留意点aries67 |
| 2025-08-21 | 【Obsidian】上で生成AIを使えるPlugIn【Smart Composer】使ってみた Smart Composer実践レポートuhd-inc |
| 2025-08-31 | オフラインでも使える!OpenAI Codex CLI + LM Studio でローカル… ローカルLLM活用設定手順classmethod |
| 2025-08-31 | Codex CLI: Running GPT-OSS and Local Coding Models… Ollama・LM Studio連携設定事例dev |
| 2025-09-03 | Ollamaと連携してOpenAI Codex CLIをローカルで試す Ollama運用方法・検証内容taneyats |
| 2025-09-04 | 【Ollama】Codex CLIでgpt-oss:20bを動かす!コンテキストサイズ… 細かなカスタマイズTips解説taneyats |
各日付順で並べることで、「Obsidian × AI」やローカルLLM関連の最新動向を時系列で俯瞰できます。
AIの画面に表示されている情報を、obsidianの文書にコピペする作業について、各方式を比較してください。メリット・デメリットという項目も追加してください。
Perplexity Pro の回答
Obsidian文書へAIの画面内容をコピペする作業に関して、各連携方式(Smart Composer、Obsidian Copilot、Custom Frames、Codex CLI+Terminal、Gemini CLI+Terminal、Claude CLI+Terminal)の比較をまとめ、それぞれのメリット・デメリットも記載します。yutashx.hatenablog
比較表
| 方式 | コピペ容易さ | コピペの流れ | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| Smart Composer | 高 | AI生成テキストをワンクリックで挿入 | Markdownに直接書き込み、手動コピペ不要 | 独自UIに慣れが要る、自由な画面間コピペには非対応 |
| Obsidian Copilot | 高 | 選択コマンドでAI出力を即反映 | ノート内任意位置へ直接反映、フォーマット保持 | Copilot対応操作範囲外だと手動コピペが必要な場合あり |
| Custom Frames | 中 | 埋め込んだAI画面で手動コピペ | Webサービスの多様な画面へのアクセス自在 | 毎回選択→切替→ペーストが必要、書式崩れやすい |
| Codex CLI+Terminal | 中 | ターミナル側から直接MD出力も可能 | コマンドでノート自動生成も可、自動保存が効く | プロンプトやコマンド記述にリテラシー必要、手動コピペも多い |
| Gemini CLI+Terminal | 中 | コマンド実行で直接ファイル保存可能 | ノート生成や追記もCLIだけで完結できる | Markdownの細かな書式保持は手動補正が必要な場合あり |
| Claude CLI+Terminal | 中 | コマンド経由でノート出力も可能 | テキストファイル直書きが早い、豊富な生成結果 | 書式整形や位置調整は手動コピペ/編集が多くなる |
詳細解説
Smart Composer
- AI出力をObsidian内でそのままノートへ挿入できるため、コピペ作業がほぼ不要。編集支援の効率が極めて高い。
- デメリットは「他のアプリからのコピペ(AI以外の画面等)」には未対応な点。note
Obsidian Copilot
- コマンド操作だけでAI要約・変換・翻訳などの結果をノートに反映可能。Markdown構造も損なわず保存される。namaraii
- Copilotの対応外な作業では普通のコピペ作業が発生することがある。
Custom Frames
- ブラウザでAIサービス画面をObsidian内に埋め込んで使えるが、出力内容は手動コピペのみ。yutashx.hatenablog
- Web表示のため装飾やレイアウトが崩れやすく、アプリ切替も発生。
- 幅広いサービス併用や資料集約には便利。
Codex CLI+Terminal / Gemini CLI+Terminal / Claude CLI+Terminal
- CLIコマンドでAI結果をMarkdownファイル化・ノート自動生成ができるため、コピペ不要なワークフローも作れる。ただし、直接コマンドを使わない場合はやはりコピペ発生。nounai-librarian
- Markdown書式保持やノートの細かな位置指定には、手動調整・コピペが続く場面もある。
まとめ
- Obsidianプラグイン側(Smart Composer/Copilot)はコピペ作業が最も省力化される。
- CLI方式は自動ノート生成や追記など自動化に強いが、柔軟な手動編集の場合はコピペ機会が残る。
- Custom Framesは画面切替とコピペ作業が必須だが、最も自由度は高い。note+5
AIが回答に使った情報源をまとめ、それらの内容についての簡単な説明文をつけた情報源集は有用で、情報源の有効活用ができた。
また、情報源のタイムラインは、情報の新旧についての、おおよその目安にもなりそう。