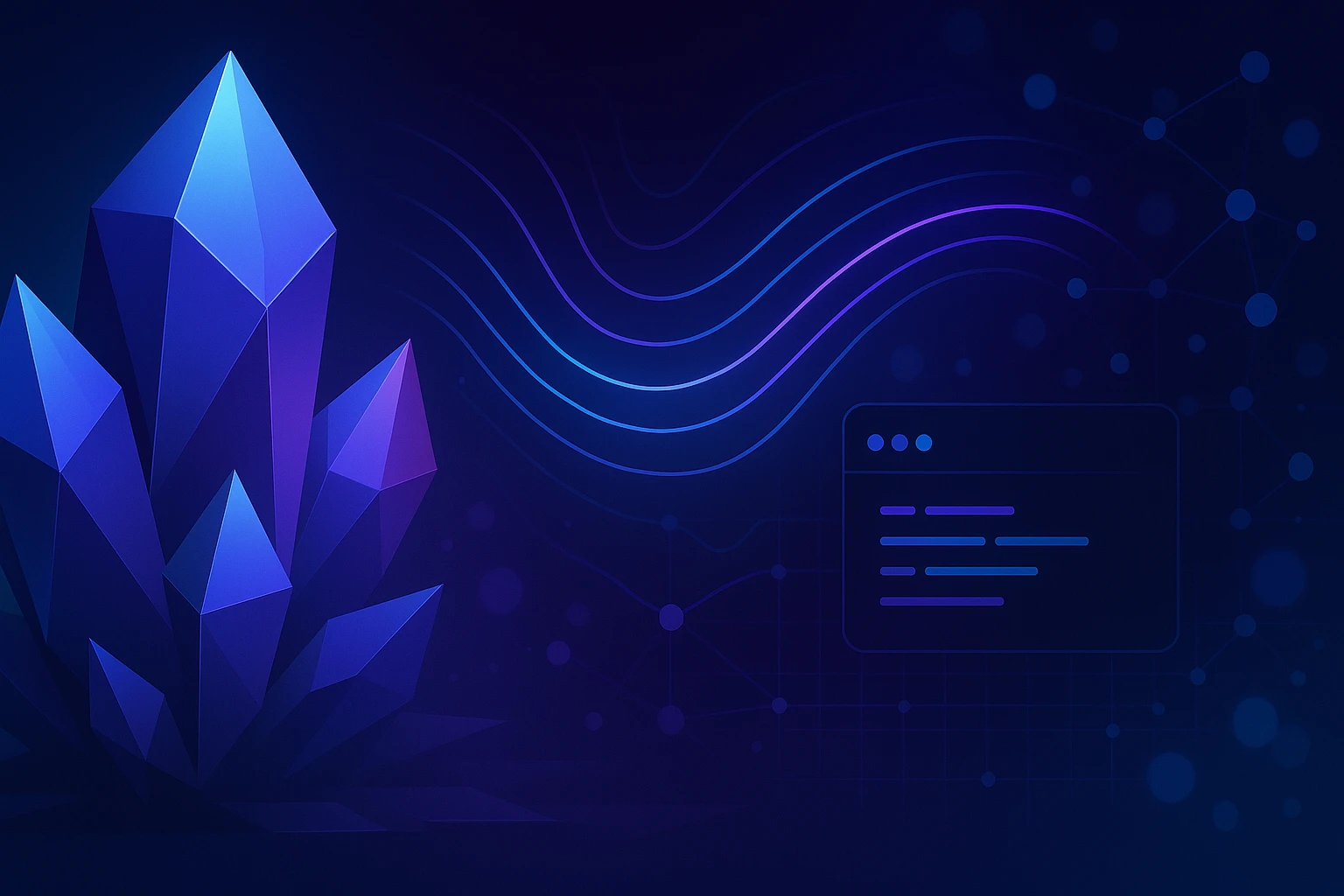下記の記事で、Obsidianと組み合わせるAIについて検討したが、今回は、Codex CLIと組み合わせて、どのようなレポートが作成できるかを調べた。
(注)本記事の内容は正確性を保証するものではない。
まずは、Codex CLIと組み合わせてレポートを作成する手順について調べた。
ObsidianとCodex CLIを組み合わせ、Codex CLIにObsidianの複数の文書を参照させてレポートを作成させることができますか
GPT 5 Thinking の回答
はい、できます。やり方のコアは「Codex CLI を“作業用フォルダ”で起動し、その中に Obsidian の対象ノート(通常Markdownに正規化済み)を並べておく」ことです。
Codex CLI はそのディレクトリ配下のファイルを読み取り・生成できるため、複数ノートを参照した集約レポートを自動作成させられます。(OpenAI Developers)
手順(最短ルート)
- Codex CLI を用意
- インストール:
npm i -g @openai/codexまたはbrew install codex。
起動はcodex。
一発プロンプト実行はcodex "~"が使えます。(GitHub)
- Obsidianノートを“通常Markdown”に出力
- Wikiリンクや埋め込みを解決したフラットな Markdown にするため、
obsidian-export(CLI)で Vault を吐き出します:cargo install obsidian-export# 初回のみ obsidian-export "/path/to/YourVault" ./notes_export
※これで[[リンク]]などが標準Markdownに変換されます。(GitHub)
(追記)obsidian-exportについては、本記事の最後の質問の欄参照。
- レポート用の作業ディレクトリを作成(安全のため分離)
mkdir -p ~/obsidian-report/{notes,output}
rsync -a ./notes_export/ ~/obsidian-report/notes/
cd ~/obsidian-report- このフォルダ配下だけを Codex に触らせる構成にすると安心です。
(Codex は基本、起動ディレクトリ配下のファイルに限定して読み書きします)。(Hacker News)
- ガイドライン(AGENTS.md)を置く
作業フォルダ直下にAGENTS.mdを作り、レポート方針を明示します
(0.34.0 では“リポジトリ直下の AGENTS.md”が優先されます)。
例:
# AGENTS.md
あなたはリサーチレポート執筆アシスタントです。
- 対象資料: ./notes 配下の *.md
- 出力: ./output/report.md(Markdown、見出し・要約・引用元ファイル名を明記)
- 方針: 章立て→要点箇条書き→詳細、重複は統合、矛盾は注記(GitHub)
- Codex に“複数ノートを読んでレポート作成”を依頼
方式A:対話UIで実行(安全・確実)
codex
# 起動後に指示:
# 「./notes 以下のMarkdownを総覧し、./output/report.md を作成。
# 章: 概要/主な論点/比較/結論。各節で出典ファイルパスを括弧で併記」- デフォルトはパッチ適用やコマンド実行のたびに承認を求める“提案モード”なので、初回はこれが無難です。(MachineLearningMastery.com)
方式B:一発プロンプト
codex "『./notes配下を横断して分析し、./output/report.md を生成』"- 1行プロンプト起動は公式ドキュメントにも記載があります。(OpenAI Developers)
方式C:非対話(CI/自動化向け)
- 一部の解説記事では“非対話/静音実行”や
execサブコマンドが紹介されています。
自動バッチで回したい場合に便利です(挙動はバージョン差分に注意)。
例:codex exec "ノート群を要約し report.md を出力"(UIなしで完了)
※最新版ではオプション仕様が変わることがあるため、運用前に現行版の docs /codex --helpを確認してください。(mlearning.substack.com)
役立つ補足
- ノートの絞り込み(タグ/フォルダ):
Obsidian 側で特定フォルダにまとめるか、エクスポート後にripgrepでタグを含むファイルだけコピーして対象を限定できます。mkdir -p notes_tagged rg -l "#レポート対象" notes_export | xargs -I{} cp "{}" notes_tagged/ - 安全設定(承認モード):
「提案 → 自動編集 → フルオート」の段階があり、まずは提案モードが推奨。フルオートはサンドボックス下で動きますが、重要作業は Git 管理と差分確認を。(Cloud Artisan) - MCP(Model Context Protocol):
Codex CLI は MCP サーバーに対応。必要ならファイルシステム等の“道具”を拡張できます(高度ですが将来の自動化に有用)。(GitHub) - 公式ドキュメント:
・Codex CLIトップ/基本概念(OpenAI Dev Docs)(OpenAI Developers)
・GitHub リポジトリ(Quickstart, Docs, 設定ファイル~/.codex/config.tomlなど)(GitHub)
まとめ
- ベストプラクティスは「Vault→
obsidian-exportで正規化→専用作業フォルダに集約→AGENTS.mdで方針固定→Codex CLIでレポート生成」。 - 初回は対話モードで安全に動作確認し、慣れたら非対話化・定期実行に進めると安定します。(GitHub)
必要なら、あなたの Vault 構成(対象フォルダ/タグ、章立てテンプレ、引用表記ルール)に合わせた AGENTS.md と実行スクリプト(bash/Makefile) をこちらで雛形化します。
正規化が必要なのは、Obsidianのマークダウン形式が独自のものであり、Codex CLIは、その独自形式のマークダウンファイルを直接読み込むことができず、読み込める形式に変更する必要があるということですか。また、そうであれば、どのような点が独自なのかを簡単に説明してください。
GPT 5 Thinking の回答
結論から言うと、「必須」ではありません。Codex CLI は普通のテキストやMarkdownをそのまま読めます。
ただし、Obsidianの“独自拡張”はアプリ側の解釈に依存していて、そのままだと他ツール(=Codex含む)がリンク解決・埋め込み展開・装飾再現をしてくれません。
そこで CommonMark寄りに正規化(リンク変換・埋め込みの展開など)しておくと、Codexに「複数ノートを横断して要約・比較」させる時に精度と再現性が上がります。
実際、obsidian-export は「Obsidianの方言 → 通常Markdown(CommonMark)」変換を目的に作られ、[[note]]や![[note]]の扱いをサポートしています。(GitHub)
Obsidianの主な“独自っぽい”点(正規化したい理由)
- Wikiリンク:
[[ページ名]]/[[ページ名|別名]](標準的な[別名](ページ名.md)とは異なる)。
変換ニーズはコミュニティでも繰り返し話題。(Obsidian Forum) - トランスクルージョン(埋め込み):
![[ノート]]、見出しやブロック単位の部分埋め込み![[ノート#見出し]]/![[ノート#^ブロックID]]。
通常Markdownにはない概念。(Obsidian Forum) - ブロック参照:行末に
^任意IDを付けてブロックを識別し、[[ノート#^ID]]で参照。通常MarkdownはブロックIDを規定しません。(Obsidian Forum) - コールアウト:引用記法の先頭に
[!info]などを置く独自の装飾(> [!tip] 等)。
CommonMark準拠のレンダラではそのままの見た目にはなりません。(Obsidian Help)
このため、Codexに“横断要約レポート”を作らせる前処理として:
- obsidian-export 等で Wikiリンク→Markdownリンク、埋め込みの解決(必要に応じ展開)をしておく
- 可能なら、出力をCommonMarkに寄せる
— といった正規化を挟むのが実務的におすすめです。obsidian-export はその用途に合致します。(GitHub)
参考:Codex CLI 自体は「起動ディレクトリ配下のファイルを読み・編集できる」ツールなので、正規化済みのMarkdownを置けば素直に使えます。(OpenAI Developers)
正規化するということは、それらの独自っぽい記載を無視する(無いものとして扱う)ということですか
GPT 5 Thinking の回答
いいえ、「無視する=捨てる」ことが正規化の意味ではありません。
目的に合わせて “変換・展開・注釈化” のいずれかに置き換えるのが正規化です。
Codex CLI はプレーンテキストを読むだけなので、独自記法を“人間と機械が同じ意味で理解できる形”に寄せればOKです。
実務でよく使う3パターン
- 軽量変換(推奨の初手)
[[ページ名|別名]]→[別名](ページ名.md)[[ページ名]]→[ページ名](ページ名.md)> [!info] …(コールアウト) →> **Info:** …(見た目近似)- タグ
#tag→ 文末にTags: #tagを追記(解析しやすく)
→ 文章構造は変えず、リンク解決と軽い装飾だけ直す方式。Codexが横断参照を理解しやすくなります。
- 埋め込みの“展開”
![[ノート]]→ そのノート本文を 引用としてインライン挿入(先頭に> From: ノート.mdなど)![[ノート#見出し]]/![[ノート#^ブロックID]]→ 指定範囲のみを引用として展開
→ レポート生成で“参照先の中身まで含めて要約”させたいときに有効。
- 注釈化(メタ情報に退避)
- ブロック参照
[[ノート#^abc123]]は本文は触らず、末尾に [^abc123]: 引用元 ノート.md の該当ブロック を自動付与 - コールアウトはそのまま残しつつ、先頭行だけ
> **Tip:**等に変換し“意味ラベル”だけ明示
→ 原文の改変を最小にしつつ、意味だけ機械可読にする方式。
具体例(Before → After)
Wikiリンク
Before: [[検索戦略|リサーチ戦略の基礎]]
After: [リサーチ戦略の基礎](検索戦略.md)埋め込み(ノート全体)
Before:
![[要件定義]]
After:
> From: 要件定義.md
> (ここに要件定義.mdの本文を貼り付け)コールアウト
Before:
> [!warning]
> この設定は実験的です
After:
> **Warning:** この設定は実験的ですブロック参照
Before:
重要ポイント ^p1
…
引用: [[議事録#^p1]]
After:
重要ポイント 〔BlockID: p1〕
…
引用: 議事録.md の該当ブロック(p1)
[^p1]: Source: 議事録.md block ^p1どう選ぶ?(方針の目安)
- 精度最優先(自動要約を強く効かせたい) → ①軽量変換 + ②埋め込み展開
- 原文保持が大事(出典管理・差分追跡) → ①軽量変換 + ③注釈化
- まず試す → ①だけで十分効果あり(リンク解決&見出し整備)
Codex CLIに効く設定のコツ
- 変換後のノートは
./notesに集約し、相対リンクが実在ファイルに解決する状態を担保 AGENTS.mdに「./notesを横断して、./output/report.mdを作る。
引用は原文ファイル名と行頭に示す」など期待動作を明文化- “埋め込みを展開した版”と“原文保持版”を分けたいなら、エクスポート先を
notes_expanded/notes_rawの2系統に
まとめ
- 正規化=「独自記法を無視して捨てる」ではなく、機械と他ツールが理解できる形に“変換・展開・注釈化”すること。
- まずはリンク解決とコールアウトの軽量変換から始め、必要に応じて埋め込みを展開する段階的アプローチが扱いやすいです。
ObsidianとCodex CLIを組み合わせて、Codex CLIに、Obsidianの複数の文書を参照して、レポートを作成させる例として、どのような内容のレポートを作成させるのが有用か、提案してください。
GPT 5 Thinking の回答(青枠はこの解釈で良いか確認した結果を示す)
了解です。Obsidianのノート束を材料に、Codex CLIに“横断参照して書かせる”と有用なレポート案を10個出します。
各案は「使いどころ/入力ノート/出力構成/Codex指示例」を短くまとめました。
1) 技術リサーチ・ブリーフ(比較表付き)
- 使いどころ:GPT/Claude/Gemini、ツール/ライブラリ比較の決定メモに。
- 入力:
notes/research/ai-tools/*(タグ#比較候補)。 - 出力:要約→比較表(長所/短所/コスト/導入手間)→推奨シナリオ→参考ノート一覧。
- Codex例
./notes/research/ai-tools を読み、差分のある主張を抽出。./output/ai_tools_brief.md を作成。最初に1ページ要約、次に比較表、最後に出典ファイル相対パスを列挙。矛盾は「争点」として別節に整理。
複数のAIツールについて記載された複数の文書(タグ「#比較候補」を付けた文書)を読み込み要約し比較表を作成
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。#比較候補付きノートを対象。
比較表は「長所/短所/コスト/導入手間/適用条件」を列に入れると実用度↑
2) 仕様統合レポート(要件定義まとめ)
- 使いどころ:機能要求/制約/優先順位を一枚に。
- 入力:
notes/specs/*、notes/requirements/*(タグ#要件)。 - 出力:目的→非機能要件→機能一覧(MoSCoW)→前提/制約→未決事項→次アクション。
- Codex例
要件ノートを統合し ./output/spec_summary.md を作成。MoSCoW分類、依存関係、未決事項は表で整理。各項目に出典ファイル名を併記。
要件定義を記載した複数の文書(タグ「#要件」を付けた文書)の内容をまとめ、目的から次アクションまでを報告する。
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。 #要件タグ+必要なら notes/specs/ フォルダで範囲を絞るとブレにくい。MoSCoW(Must/Should/Could/Won’t)分類推奨。
3) 会議横断議事録 → アクション集約
- 使いどころ:複数回の打合せからToDo・担当・期限を一括抽出。
- 入力:
notes/meetings/2025-*/**.md(タグ#action)。 - 出力:決定事項/保留事項/アクションアイテム(担当・期日・出典)/論点ログ。
- Codex例
会議ノート群からアクションを抽出し ./output/actions_board.md を作る。テーブル列: Task, Owner, Due, Source, Status(初期値Open)。
複数の議事録(タグ「#action」を付けた文書)を参照し、決定事項などをまとめて報告する。
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。 #actionタグの行(決定/ToDo)を抽出し、表「Task/Owner/Due/Source/Status」にまとめる想定。
4) ブログ月間コンテンツ計画 & 下書き種
- 使いどころ:Obsidianで書き溜めたネタを月間計画に落とし込む。
- 入力:
notes/blog/ideas/*、notes/clippings/*(タグ#blog候補)。 - 出力:月間カレンダー案、各記事の骨子(見出し/H2-H3)、内部リンク案、画像の指示。
- Codex例
ブログ候補をスキャンし ./output/blog_plan_YYYY-MM.md を作成。週ごとに3本配置。各記事は要約100字、H2案3つ、内部リンク候補3つを提示。
ブログ記事のネタを記録した複数の文書(タグ「#blog候補」を付けた文書)を参照して、所定の優先順位を設定し、月間計画に落とし込む。
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。 #blog候補対象。優先順位は「検索需要/独自性/下書き完成度/画像準備」の重み付けを明記しておくと自動化しやすい。
5) プロジェクト進捗ダイジェスト(KPI/リスク)
- 使いどころ:週次ステータス報告の自動化。
- 入力:
notes/project/*(#進捗、#課題タグ)。 - 出力:今週の進捗→KPI推移(表)→ブロッカー→リスク登録票→来週計画。
- Codex例
進捗/課題ノートから ./output/weekly_status.md を生成。「KPI表」「リスク表」をMarkdown表に。リスクはImpact×Likelihoodで優先度。
プロジェクトの進捗や課題を記載した複数の文書(タグ「#進捗」やタグ「課題」を付けた文書)を参照し、今週の進捗や来週計画を報告・提案する。
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。 タグは #進捗 と #課題(ハッシュ付き)で統一推奨。
KPIは時系列表、リスクはImpact×Likelihoodで優先度算出。
6) 不具合・トラブルシュート総括(RCA)
- 使いどころ:障害ノートを横断して再発防止策を明文化。
- 入力:
notes/incidents/*、notes/troubleshoot/*。 - 出力:症状→原因仮説→検証ログ→恒久対応(SOP化)→既知の回避策。
- Codex例
障害ノートを統合し ./output/rca_compendium.md。発生日順のタイムラインと、共通原因のクラスタリング結果を章でまとめる。
障害内容と対応策を記載した複数の文書を参照して内容をまとめ、再発防止策を明文化する。
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。 入力は障害/対応ノート。出力は「症状→原因仮説→検証→恒久対策→回避策→再発条件」。
原因の共通パターンをクラスター化。
7) 文献レビュー(論文・記事サーベイ)
- 使いどころ:AI/開発手法などの文献ノートを体系化。
- 入力:
notes/papers/*、notes/reading/*(タグ#要約)。 - 出力:研究テーマ→主要論点→比較表(データ/手法/結果)→ギャップ→今後の仮説。
- Codex例
文献要約を統合し ./output/lit_review.md。それぞれの出典に短い引用(<=2文)と批判的コメントを付与。
複数の文献ノート(タグ「#要約」を付けた文書など)を読み込み、比較表作成、今後の仮説などの報告を行う。
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。 #要約や#paperを対象。比較表は「データ/手法/評価指標/結果/限界/再現性」。
最後に“ギャップ”と“次の仮説”。
8) 投資メモ統合 → 戦略サマリ(新NISA)
- 使いどころ:商品メモ・家計前提・税制ノートから戦略案を1枚に。
- 入力:
notes/finance/nisa/*、notes/finance/expenses/*。 - 出力:前提(家・車・修繕・インフレ)→積立配分→想定レンジ→点検チェックリスト。
- Codex例
金融ノートを統合し ./output/nisa_strategy.md。配分は表(銘柄/比率/根拠)。前提はソースノートを括弧で併記。
投資商品について記載した複数の文書を読み込み、前提条件、積立配分などの投資戦略を提案する。
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。 投資商品ノート+家計前提ノートを入力。
配分表(銘柄/比率/根拠/想定リスク)と見直し条件(トリガー)を明記。
9) ゲーム/PC設定チューニング手順書まとめ
- 使いどころ:ドライバ差分・設定ログ・ベンチ結果を一枚に。
- 入力:
notes/pc/gaming/*(タグ#設定、#計測)。 - 出力:環境表→ドライバ履歴→設定手順→再現手順→問題と回避策→ベンチ比較。
- Codex例
ゲーム設定ノートから ./output/tuning_guide.md。「変更→効果→副作用」を表で。元ノートのスクショ参照箇所は見出しリンクで。
ドライバ差分・設定ログ・ベンチ結果について記載した複数の文書(タグ「#設定」やタグ「計測」を付けた文書)を読み込み、環境表やベンチ比較などの報告を行う。
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。 #設定・#計測対象。環境表(CPU/GPU/ドライバ/OS/BIOS)とベンチ比較、変更→効果→副作用の対応表を作成。
10) QZSS/DCX テレメトリ解析ダイジェスト
- 使いどころ:観測ログ・解析メモをまとめ、異常や傾向を俯瞰。
- 入力:
notes/gnss/qzss/*、notes/logs/*。 - 出力:観測条件→デコード結果サマリ→異常事例→時系列グラフ(説明文)→次の実験。
- Codex例
GNSS関連ノートから ./output/qzss_digest.md。異常パターンは箇条書きで分類し、各パターンに再現手順と出典ノートを付ける。
観測ログ・解析内容を記載した複数の文書を読み込み、異常や傾向について報告を行う。
<GPT 5 Thinking の回答>
→ OK。 観測ログ/解析ノートを入力。時系列サマリ、異常パターン一覧(条件/頻度/再現手順/出典)と今後の実験計画を出力。
すぐ使えるフォルダ & AGENTS.md ひな形
obsidian-report/
├─ notes/ # obsidian-export 後のノート群を入れる
├─ output/ # Codexの成果物
└─ AGENTS.mdAGENTS.md(例)
あなたはリサーチレポート執筆アシスタントです。
- 対象: ./notes 配下の .md(Obsidian由来、リンクは相対参照)
- 出力: ./output/report.md(章立て・要約・表・出典相対パスを明記)
- ルール:
1) 重複は統合、矛盾は「争点」として分離
2) 重要表はMarkdown表で
3) 各節末に参照元ファイルを列挙実行ワンライナー
codex " ./notes を横断して分析し、./output/report.md を作成。章: 概要/主要論点/比較/結論。表を活用し、出典は相対パスで併記。"ヒント(精度と再現性を上げるコツ)
- 「対象ノートの入り口を絞る」:特定フォルダ/タグのみを
notes/に入れる。 - 「出典併記を徹底」:後で原文をたどれるように、各段落末に
(source: path/to.md)。 - 「テンプレ固定」:AGENTS.mdに章立て・表の列名・禁止事項(冗長な脚色等)を明記。
必要なら、上記10案のうち優先度の高いものを選んで、AGENTS.mdの完成版と実行スクリプト(Makefile / npm-scripts)をその場で作ります。
正規化したことにより有用となった情報を活用した、レポート作成案はありますか
GPT 5 Thinking の回答
あります!“正規化のおかげで初めて(もしくは格段に)やりやすくなる”レポート案を、活用する正規化成果(リンク解決・埋め込み展開・ブロックID注釈・タグ/Frontmatter抽出 等)とセットで提案します。
各案はそのままCodex CLIに投げやすい短い指示例付きです。
1) 「争点マップ」レポート(矛盾・重複の特定)
- 正規化の効きどころ:
[[wikilink]]→[text](path.md)により同一テーマの集約、![[…]]展開で引用本文の可視化 - 出力:テーマごとに「主張A/主張B/エビデンス/該当ファイル/引用抜粋」
- Codex指示例
./notes を横断し、同一テーマで相反する記述を抽出。./output/issue_map.md に「テーマ/立場A/立場B/根拠/出典相対パス/引用(<=120字)」の表で出力。似た主張は統合し、重複は1行にまとめる。
同じwikilinkを有する複数の文書を参照し、それらの矛盾・重複を特定して、複数の主張やエビデンスなどを報告する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 同一/同義の wikilink で束ね、主張の重複統合と相反主張の抽出を行い、根拠(引用/出典)付きで整理。
2) 「引⽤コンコーダンス」レポート(ブロック参照の索引)
- 正規化の効きどころ:
[[note#^blockID]]→ 注釈化済み(行末注釈など) - 出力:BlockIDごとに「要約/初出ノート/被参照元一覧/引用回数」
- Codex指示例
注釈化された BlockID を走査し、./output/block_concordance.md を作成。各IDに要約(<=1行)、出典、参照しているノート一覧、参照回数を列挙。
blockIDごとに要約や引用回数などを報告する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 ^blockID 単位で要約・初出・被参照元・参照回数を一覧化。
3) 「埋め込み展開サマリ」(原典と派生の追跡)
- 正規化の効きどころ:
![[…]]を本文展開しているため、派生箇所の追跡が可能 - 出力:「原典ノート → どのノートにどの節が引用されたか」の表+重複引用の集計
- Codex指示例
展開済み埋め込みを検出し、./output/embedded_usage.md。列: 原典, 引用先, 引用開始行, 範囲(H2/H3), 要約(<=80字)。原典ごとの引用件数を末尾に集計。
![[…]]を基にして、原典と派生箇所をまとめて報告する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 ![[…]] を展開して、原典(埋め込まれ元)→引用先(派生)の対応表を作成。
4) 「用語集(Glossary)自動整備」
- 正規化の効きどころ:リンク解決済みで同義語/別名(
[[用語|別名]]→[別名](用語.md))が拾える - 出力:用語/別名/定義(初出文から抽出)/関連ノート/初出日(YAMLや日付行があれば)
- Codex指示例
別名リンクを解析し、./output/glossary.md。各用語につき定義(<=2文)、別名、関連ノート(トップ3)、初出の出典パスを列挙。
別名リンクを解析し、用語、別名、定義、関連ノートなどをまとめて報告する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 [[用語|別名]] などから別名正規化→定義・関連ノート(トップN)を付与。
5) 「タグ×テーマのヒートマップ報告」
- 正規化の効きどころ:Frontmatter
tags:や本文#tagを抽出統一済み - 出力:タグ別のノート数・主要テーマ(H2)出現回数・空白(薄い領域)の提案
- Codex指示例
抽出済みタグを集計し、./output/tag_heatmap.md。表: Tag, NoteCount, 主要見出し上位3, 補強すべき空白領域(提案)。
タグの情報をまとめて、出現回数、空白領域などを報告する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 タグ頻度・共起(よく一緒に出る見出し/タグ)を集計し、空白領域(未カバー)を提案。
6) 「内部リンク監査・修繕計画」
- 正規化の効きどころ:相対パス化されたリンクでリンク切れ/孤立ノートが機械検知可能
- 出力:Broken links一覧/孤立ノート(被リンク0)/修繕優先度と案
- Codex指示例
相対リンクを検証し、./output/link_audit.md。Broken/Orphan/重複タイトルの3節に分け、修繕手順(改名・リダイレクト・要約追加)を提案。
相対パスを検証し、リンク切れノート、孤立ノート、修繕優先度などを報告する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 相対パスを検証してリンク切れ/孤立ノート/重複タイトルを検出し、修繕優先度と対応案を出す。
7) 「決定事項DB」レポート(会議横断の決定ログ化)
- 正規化の効きどころ:コールアウト
[!decision]を> **Decision:**等に変換 → 機械可読 - 出力:Decision/根拠引用/期日/責任者/出典(行リンク)
- Codex指示例
Decisionコールアウトを抽出し、./output/decisions.md。列: Decision, Rationale(引用<=150字), Owner, Due(推定), Source(path#行)。
コールアウト [!decision] を、機械が可読な形式の情報に変換する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:ほぼOK。 [!decision] 等を機械可読な行構造(Decision/Owner/Due/Source など)に抽出・正規化し、DB(Markdown表)に。
8) 「比較表 一括生成」(機材・ツール・手順の横断比較)
- 正規化の効きどころ:埋め込み展開で断片的メモの統合が可能、リンク解決で比較対象の束ねが容易
- 出力:対象×評価軸(コスト/効果/副作用/前提)+推奨シナリオ
- Codex指示例
類似テーマのノート群から比較軸を抽出し、./output/comparison.md。表: Item, Pros, Cons, Cost, Setup難度, 推奨シナリオ, Source。
埋め込みを示す表現(![[A]]など)を認識し、その本文を引用として貼り付けたり、リンクを示す表現([[候補A]]など)を認識し、パスも含めてリンク先のファイルを特定した後、特定の軸での比較を行う。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 ![[A]] を引用として展開し、[[候補A]] をリンク解決して同一対象に束ね、指定の比較軸(Pros/Cons/Cost…)で表化。
9) 「引用一言サマリ集」(ブログ素材化)
- 正規化の効きどころ:展開された引用が既に本文内に存在するため、短い抜粋を安全抽出
- 出力:トピック別に「キーメッセージ(<=120字)/出典/内部リンク」
- Codex指示例
引用候補を抽出し ./output/one_liners.md。各トピックで3本ずつ短い抜粋を作り、元ノートへ相対リンクを付す。
埋め込みを示す表現(![[A]]など)を認識し、その本文を引用として貼り付ける前処理を行った後、特定ルールに従い、ブログ記事の見出しや “つかみ”に使える短文を生成し提案する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 先に埋め込み展開→抽出ルール(箇条書き/見出し直後/コールアウト)で≤120字の“つかみ”文を生成し、出典併記で提案。
10) 「知識の空白(未記述領域)検出レポート」
- 正規化の効きどころ:タグ・リンク網が素直に解析できるため、周辺はあるが本体が無い“空ノート候補”を抽出
- 出力:「関連タグは多いが中心ノート不在」のテーマ一覧+下書き見出し案
- Codex指示例
タグとリンク網から中心ノート不在テーマを抽出し、./output/gaps.md。テーマごとにH2見出し案(3つ)と埋めるべき具体項目を列挙。
例えば、タグ「#LCP」は複数のノートにあるのに、そのテーマに関するまとめノート(LCP.md)がない場合など、中心となるノートが無い状態を検出して報告する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 例のとおり、頻出タグ/言及は多いのに中心ノートが無い(または中身が薄い)テーマを検出して報告。
(追記) “空ノート候補”の他のパターンについては本記事の最後の質問の欄参照。
11) 「出典厳密化レポート」(脚注/参照統一)
- 正規化の効きどころ:ブロック参照が脚注化されているため、脚注→本文の往復が可能
- 出力:脚注欠落・曖昧参照の修正候補、表記ゆれの統一案
- Codex指示例
脚注と本文の対応を検査し、./output/citations_fixlist.md。欠落脚注、重複脚注、出典不明の箇所を列挙し、統一スタイル案を付記。
脚注と本文の対応を検査し、欠落脚注や、出典不明の箇所の報告を行う。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 脚注↔本文の対応を照合し、欠落脚注/重複/出典不明を列挙。表記ルール案(統一スタイル)も提示。
12) 「タイムライン統合(時系列サマリ)」
- 正規化の効きどころ:Frontmatter
date:や見出し日付、ファイル名日付が一貫抽出可能 - 出力:期間別の出来事/決定/アクション/成果と課題
- Codex指示例
日付メタを統合し ./output/timeline.md。月→週→出来事の粒度で整理し、各出来事に出典パスを併記。
各種日付を統合し、時系列サマリを作成する。
<GPT 5 Thinking の回答>
解釈:OK。 Frontmatter date:, 見出し日付, ファイル名日付等を統合し、出来事/決定/成果・課題を時系列に要約。
すぐ使える AGENTS.md 断片(正規化成果を活用するルール)
- リンクは相対パスで存在確認できるもののみ引用し、各節末に (source: path/to.md) を付す
- 展開済みの引用は「> 」で2行以内に要約して併記(原文の意味を変えない)
- BlockID脚注がある場合は該当箇所へ行内注釈〔BlockID: xxx〕を残す
- タグ/Frontmatterがある場合、章頭に Tag と Date を列挙してから本文に入る実行ワンライナー(テンプレ)
codex " ./notes を横断し、(上記いずれかの)レポート仕様で ./output/<name>.md を作成。出典は相対パス、引用は<=120字、表はMarkdownで。欠損や矛盾は『争点/修繕案』節に分離。"必要であれば、上記12案から優先度の高い2~3本を選んで、完成版AGENTS.mdと実行スクリプト(Makefile/npm-scripts)をその場で作ります。
正規化処理を行うことによって活用方法が広がるが、予め、所定のタグを付与しておくとかの処理が必要な場合もある。複数のノートに一括して特定のタグを付与することも必要になる。
本記事の活用事例では、複数の文書に特定のタグを付けて、処理対象の文書とする例が多かったが、処理対象を、フォルダ内の全文書とすることもできると思うので、事例によっては、こちらの方法の方が楽かもしれない。
検索等により処理対象の文書を絞りこめれば、それらの文書を別フォルダにコピーし、そのフォルダでCodex CLIを起動し処理を行った方が、vault全体に対するリスクを低減できる。正規化により文書を書き換えてしまうことがあるので、間違ってオリジナルの文書を書き換えてしまうことがないように。
(追記) [空ノート候補」とは何かなど、GPT 5 Thinkingの回答で分かりにくかった点などを追加質問した。
| 質問 | GPT 5 Thinkingの回答 |
|---|---|
| 「cargo install obsidian-export」のcargoとは何ですか。どのような環境で有効な命令ですか。 また、obsidian-exportの情報源を教えてください。 | 要点だけサクッと👇 cargoとは? Rustのパッケージマネージャ兼ビルドツールです。依存関係の取得、ビルド、配布、 crates.ioへの公開まで面倒を見ます。(doc.rust-lang.org)どんな環境で使える? macOS/Linux/Windows(PowerShell・WSL含む)のターミナルで有効なコマンドです。通常は rustup でRustツールチェインを入れると cargo も同時に入り、~/.cargo/bin(Windowsは%USERPROFILE%\.cargo\bin)に配置されます。(doc.rust-lang.org)cargo install obsidian-exportの“情報源” obsidian-export は Obsidianの独自拡張を標準Markdown(CommonMark寄り)に書き出すCLI/ライブラリ。公式README(GitHub)に下記内容が明記されています。 「Wikiリンク [[note]]・埋め込み ![[note]] をサポート」、「事前ビルドのバイナリあり」、 「Cargoでのビルド/インストール手順」 crates.io でもパッケージ情報が掲載されています。(GitHub) インストールの選択肢 Rust環境がある → cargo install obsidian-exportRust環境を入れたくない → GitHubのReleaseからOS向け事前ビルド版を取得 (どちらもREADMEに記載)(GitHub) 基本の使い方(参考) obsidian-export /path/to/vault /path/to/exported/Vault内のノートを再帰的にエクスポートします(除外設定や .gitignore 連携も対応)。(GitHub) 必要なら、macOS(Catalina想定)での rustup→cargo→obsidian-export 導入ステップをあなたの環境に合わせて具体化します。 |
| 『10) 「知識の空白(未記述領域)検出レポート」で、「周辺はあるが本体が無い“空ノート候補”を抽出」、「出力:「関連タグは多いが中心ノート不在」』と回答されているが、具体的には、どのようなノートがないということか、分かりやすく教えてください。 | わかりやすく言うと―― 多くのノートで何度も言及されている“中心テーマ”なのに、 そのテーマ専用の“まとめノート(ハブ)”が存在しない状態です。 または、ファイル名だけあって中身がほぼ無い(数行・メモ1行)“空ノート”のまま。 以下のような「ない・足りない」が該当します。 具体例(こういうノートが“ない/空”) 1. 用語の基礎ページがない 各所で #LCP タグや「LCP 改善」と書かれているのに、notes/glossary/LCP.md のような定義・測り方・対策をまとめた基礎ノートが存在しない。2. 比較のハブがない 「候補A/B/C」の個別ノートはあるのに、 それらを横並び比較する総括ノート(例: tools/画像最適化_比較.md)がない。3. プロジェクトのREADME/概要がない specs/、meetings/、tasks/ が充実しているのに、目的・範囲・タイムライン・成果物を一枚にまとめた project/README.md がない。4. 決定事項のインデックスがない 各議事録に Decision が散在しているのに、 Decision 一覧(担当・期日・出典付き)の decisions/index.md がない。5. RCA(原因分析)の総括がない たくさんの障害ノートはあるのに、 共通原因・再発防止策を横断で整理した incidents/RCA_summary.md がない。6. 用語集/人物・システム辞書の見出しがない 多数のノートで「NVIDIA DLSS」「QZSS DCX」などに触れているのに、 定義・略語展開・関連リンクを集約する glossary/…md がない。7. 手順の標準形(SOP)がない “毎回の手順”が議事録や断片メモに散らばっていて、 安定した手順書( sop/デプロイ手順.md など)がない。8. タイムラインの俯瞰がない 週報・日報はあるのに、 主要イベントだけを並べた timeline/年次サマリ.md がない。9. タグの中心ページ(タグハブ)がない #Web性能 が多用されているのに、そのタグの目次ページ(関連ノートをセクション分けで並べる)がない。 10. 出典/引用ポリシーの統一ページがない 脚注や出典表記が揺れているのに、 表記ルールと例を示したガイド( guides/citation_style.md)がない。“空ノート候補”の機械的な見つけ方(中身が薄いタイプ) 存在はするが中身が極小:文字数しきい値(例:< 200字、見出しのみ等) 参照は多いのに本文なし:被リンク(バックリンク)数が高いのに本文が数行 タイトルだけで本文が箇条書き1行、リンクだけで説明がない Frontmatterだけ( title: …, tags: …)で本文未記入検出の考え方(簡単なルール) タグ頻度 vs ノート有無 あるタグ(例: #LCP)の出現数が閾値を超えるのに、glossary/LCP.md や topics/LCP.md が無い → 中心ノート不在リンク先の集約キー vs ハブ有無 [LCP](topics/LCP.md) へのリンクが多いのに、そのファイルが空/短文のみ → 空ノート被リンクの偏り ある用語への被リンク数が多いのに、その用語ノートの本文が薄い (=「みんな参照しているのに中身がない」) 報告の出力イメージ(レポート) # 知識の空白レポート ## タグは多いが中心ノート不在 - テーマ: LCP 兆候: #LCP の出現 37件 / 中心ノートなし 推奨: glossary/LCP.md を新規作成(定義/計測/対策/関連リンク) - テーマ: 画像最適化 兆候: 候補A/B/Cノートあり / 比較ハブなし 推奨: tools/画像最適化_比較.md(表: Pros/Cons/Cost/適用条件) ## 空ノート(存在するが中身が薄い) - ファイル: project/README.md(本文98字・被リンク14) 推奨: 目的/範囲/KPI/里程標/関係図を追記 - ファイル: incidents/RCA_summary.md(見出しのみ) 推奨: 共通原因クラスタ・恒久対策・影響範囲を追加まとめ “中心ノート不在”=頻出テーマを束ねるハブ(定義・比較・目次・総括)が無い。 “空ノート”=ハブはある体裁だが中身が伴っていない。 この2つを見つけて埋めることで、再利用性・検索性・説明責任が一気に上がります。必要なら、あなたのVault向けに「検出ルール+雛形ノート(README/比較表/用語集/SOP)のテンプレ」を作成します。 |
| 「埋め込み展開で断片的メモの統合が可能、リンク解決で比較対象の束ねが容易」とは、具体的には、どのようにするということですか | いい質問です。ここで言う「埋め込み展開」= ![[ノート]] / ![[ノート#見出し]] / ![[ノート#^ブロックID]] をその場に本文として差し込むこと「リンク解決」= [[wikilink]] / [[ページ名|別名]] を [テキスト](相対パス.md) に直し、同じ対象を同一キーで束ねられる状態にすることです。これで、断片がバラけたメモを“1つの土俵”に乗せ、比較対象の自動集約がやりやすくなります。 1) 埋め込み展開で「断片的メモ」を1枚に集約する 具体ルール ![[A]] → > From: A.md に続けて A.md の本文を引用として貼り付け![[A#B]] → A.md の見出しBセクションだけを抽出して引用![[A#^xyz]] → A.md の ^xyz が付いたブロックだけを抽出して引用どこから引用したかがわかるように、行頭に出典(相対パス+位置)を付記 Before(集約ノート) 候補Aの評価 ![[候補A#特長]] 候補Bの評価![[候補B#^k1]]After(展開済み) ## 候補Aの評価 > From: ./notes/tools/候補A.md#特長 > – 高速に動作 > – 日本語対応 > – 無料枠あり ## 候補Bの評価 > From: ./notes/tools/候補B.md#^k1 > ベンチ結果: 条件XでスループットY → こうしておくと、Codex/Gemini/Claude いずれも “目の前の単一ファイルの本文”として根拠を読めるので、横断要約や引用抽出が安定します。 2) リンク解決で「比較対象」を束ねる 具体ルール [[候補A]] → [候補A](./notes/tools/候補A.md)[[候補A|A]] → [A](./notes/tools/候補A.md)変換後、リンクの「指し先パス」=比較キーとして扱える(同名・別名も同一キーに統合可能) なにが嬉しい? どのノートでも 「候補A」に向くリンクは同じ相対パスになる → 「候補A」について書かれた断片を機械的に収集できる “別名”が混在しても、URLが同じ=同一対象と判断可能 → 重複統合や表の1行に集約ができる ミニ例:対象インデックスの作り方(概念) [候補A](./notes/tools/候補A.md) を含むファイル → list_A.txt [候補B](./notes/tools/候補B.md) を含むファイル → list_B.txt … この “対象 → 参照しているノート一覧” を下敷きにすると、Codexへ 「対象ごとに Pros/Cons/Cost を抜き出して比較表にして」 の指示が通りやすくなります。 3) 実務ワークフロー(最小構成) obsidian-report/ ├─ notes/ # 正規化済みノート(リンク解決済、必要なら埋め込み展開済み) ├─ output/ # 生成物 └─ AGENTS.md # 埋め込み/出典の扱い、比較軸などのルールを明文化 変換(例) まず obsidian-export 等で Wikiリンク→Markdownリンク(必要に応じて埋め込み展開も済ませる)もし埋め込みを後段でやるなら、Codexに「![[…]] があれば相手先を開き見出し単位で引用を差し込む」と明記 Codexへの指示例(比較レポート) ./notes を横断して、同一の相対リンク先(=比較対象)ごとに情報を集約し、 ./output/comparison.md を作成。 表の列: Item, Pros, Cons, Cost/License, Setup難度, 典型ユースケース, Sources – 引用は <=120字、各セル末尾に (source: 相対パス#位置) を付与 – 同義語/別名もリンクの指し先が同じなら同一行に統合 4) まとめ(役割分担のイメージ) 埋め込み展開:離れて存在する“根拠本文”をその場に持ってくる(読む側=LLMが迷子にならない) リンク解決:ラベルぶれを同一のリンク先パスで吸収し、対象ごとに束ねやすくする この2つを先にやっておくと、LLM側のプロンプトは「集約・比較・出典併記」に集中でき、再現性が高いレポートが作りやすくなります。必要なら、あなたのVault構成に合わせた変換ルール(正規表現/スクリプト雛形)とAGENTS.mdを作ります。 |
| 正規化した方が良いという事情は、Codex CLIの代わりに、Claude codeを使う場合も同じでしょうか | 結論:ほぼ同じ事情で、正規化はやった方が安全です。 Claude Code もターミナル常駐の“エージェント型コーディングCLI”で、基本はプロジェクト配下のテキスト/ファイルI/Oを使って作業します。Obsidianの独自記法( [[wikilink]] や ![[埋め込み]] など)を自動で解決・展開する保証はありません。そのため、Codex CLI と同様に CommonMark寄りへ変換(リンクを通常Markdownに、埋め込みは展開 or 注釈化)しておくと、横断要約や引用・出典付けが安定します。(Anthropic)参考: Claude Code 公式ドキュメント(概要・CLIリファレンス・IDE連携)— ターミナルで動くエージェント型ツールで、設定やメモリはあっても独自マークダウンの解決機構は前提になっていません。(Anthropic) Obsidianの独自記法(内部リンク [[...]]、![[...]] の埋め込みなど)の公式ヘルプ。これらは通常Markdownと互換ではないため、他ツールで意味を維持するには変換が有効です。(Obsidian Help)obsidian-export(Rust製CLI)— Vaultを“通常Markdown”へ書き出す実績ある方法。 cargo install obsidian-export またはリリースのバイナリで導入できます。(GitHub)要するに、Codex CLIでもClaude Codeでも「Obsidian固有→標準Markdown」の軽量変換+必要に応じた埋め込み展開を挟んでおくのがベストプラクティスです。 |
| 正規化した方が良いという事情は、Codex CLIの代わりに、Gemini CLIを使う場合も同じでしょうか | 結論:Gemini CLIでも事情はほぼ同じで、Obsidian独自記法([[wikilink]]、![[埋め込み]] など)をそのまま“理解・解決”してくれるわけではありません。Gemini CLIはターミナル上でファイルを読み書きしつつ対話する汎用エージェントで、内容はプレーンテキストとして扱います。よって CommonMark寄りに正規化(リンク変換/埋め込みの展開や注釈化)しておくほうが、横断要約や比較レポートが安定します。(GitHub) なぜ正規化が効くの? Gemini CLIは“ローカルのプロジェクト配下を読んで作業”するツールで、リポジトリやフォルダ内のファイルをコンテキストに処理します(Obsidian専用レンダラではない)。(Google for Developers) 一方で Obsidianの内部リンク/埋め込みは独自拡張( [[ノート]], [[ノート|別名]], ![[ノート#見出し]] 等)で、通常Markdownとは互換でないため、他ツールが意味を取りづらい。(Obsidian Help)そのため、 [[…]] → [text](path.md) に直し、![[…]] を展開 or 注釈化しておくと、リンク追跡・出典併記・重複統合がやりやすくなります。必要なら obsidian-export のようなエクスポータも利用可。(GitHub)実務メモ(Gemini CLIでObsidianノートを使うとき) 対象ノートを正規化して1つの作業ディレクトリに集約(相対リンクが実ファイルに解決できる状態)。 プロンプトに「./notes を横断し、./output/report.md を作る。各節末に (source: 相対パス)」等の明示ルールを記す。 埋め込みは用途に応じて:要約に混ぜたい→展開、原文重視→注釈化で“参照だけ残す”。 参考:Gemini CLIの公式ドキュメント/リポジトリ/ハンズオン(機能と前提がまとまっています)。(Google for Developers) 必要なら、あなたのVault構成に合わせた簡易コンバータ(リンク変換・埋め込み展開)とGemini CLI用プロンプト雛形をこちらで作成します。 |
上記質問で、“空ノート候補”に該当するノートの種類が多数回答されたので、それらのノートがあった方が良いという考え方もあることが分かった。それらのノートの要否はユーザー次第だが、処理対象文書の絞り込みに使うのかもしれない。“空ノート候補”が自動的に作成されないなら、自動的に作成するプラグインがあってもよさそう。“空ノート候補”を作成する手間がかかるのだから。
(追記) “空ノート候補”を自動的に作ってくれるプラグインがないかどうかを調べた。
“空ノート候補”のノートを自動的に作成してくれるプラグインは無いのですか
(追記) 下記の回答で紹介されたプラグイン(QuickAdd + Templater以外)は、メジャーなプラグインではなさそうなので使用には注意。
GPT 5 Thinking の回答
短答:“タグ頻度などから自動でハブ用の空ノートを量産”する専用プラグインは見当たりません。
ただし、未作成リンク(unresolved/dangling links)を一覧→必要分だけ一括で作る/その場で作る系の手段はあります。
近い解決策
- Dangling Links(コミュニティプラグイン)
ボルト内の「未解決リンク」をサイドパネルに一覧表示。そこから未作成ノートの洗い出し・対処ができます。(GitHub) - Note Auto Creator(コミュニティプラグイン)
文章中で新しいリンクを挿入したときに、存在しないリンク先ノートを自動作成できます(設定可)。“リンクしたら即 stub を切る”運用に向きます。(Obsidian Forum) - Find unlinked files and unresolved links(旧来の支援プラグインの系統)
未リンクファイル/未解決リンクの一覧ページを生成して対応しやすくします。(Obsidian Forum)
コア機能の補足
- Obsidian自体も未解決リンクをクリックすると新規ノートを作成できます(既定動作)。大量自動生成ではありませんが、手動で素早く作る用途に十分です。(Reddit)
まとめ
- “知識の空白(中心ノート不在)を検出して自動でハブノートを作る”というレベルの自動化は未確認。
- 代わりに、Dangling Links で候補を洗い出し → Note Auto Creator(または既定動作)で必要な stub を作る運用が現実解です。
- 必要なら、タグ頻度や被リンク数を指標に作成対象を提案するレポートをCodex/Geminiで先に出し、その結果をもとに上記プラグインでノート作成…という2段構えを設計します。
Perplexity Pro の回答
Obsidianには、「空ノート」(未作成の基礎ページやハブノート等)の作成を完全自動化する専用プラグインは一般には存在しませんが、似た機能を手動または部分自動で実現できる方法や拡張はいくつか存在します。note
空ノート自動作成に近いプラグイン・機能
- Missing Link File Creator
- 未作成のリンク先ファイル(=空リンク=空ノート)を自動で一括生成するプラグインが存在します。
- Vault内のリンクを解析して、実体の無いリンク先ノート(例: [[LCP]]など)をまとめて新規作成できるため、人手で新規ノートを繰り返し生成する手間を削減できます。obsidianstats
- QuickAdd + Templater
- 「手順の基礎ノート」「プロジェクトREADME」「比較ノート」など、自分で雛形を作って、指定のフォルダや命名規則で自動生成できます。note
- 完全自動ではありませんが、「無い場合のみ自動で作る」など一部自動処理が可能です。
- 空リンク(未作成ノートリンク)クリックによる生成
- Obsidian本体の仕様として、未作成のノートへのリンクをクリックすると即座に新規ノートが作成されます。note
- 例えば、タグのインデックスや比較ページなど、リンクだけ先に書いておき、リンクをクリックするだけで空ノート作成ができます。
注意点
- どの方法でも「基礎ノートの構造」やテンプレートの詳細までは人手で作り込む必要があります。
- 既存ノート内のリンクやタグを集計し、「必要だけど未作成の基礎ノート候補」を列挙→一括生成する流れは、「Missing Link File Creator」+「テンプレート」などの組み合わせである程度実現できます。scuti
- 用途ごと(用語集・比較ハブ・決定事項など)の自動化には個別のテンプレート設計が推奨されます。
参考プラグイン名
| 機能 | プラグイン名 | 備考 |
|---|---|---|
| 未作成リンクから空ノート自動生成 | Missing Link File Creator | 未作成ノートを一括作成obsidianstats |
| テンプレートから自動生成 | QuickAdd, Templater | 雛形付きノート作成note |
| 自動リンク付与(ノート自動生成補助) | Auto Linker | 用語の自動リンク化サポートnote |
このように、未作成の定義用ノートやハブページの完全自動一括生成を公式・主要コミュニティプラグイン1本で完結するものは存在しませんが、Missing Link File CreatorやQuickAdd、Templaterなどを組み合わせてほぼ自動化することができます。note
タグの「まとめノート」を作成する目的については下記記事でも紹介している。