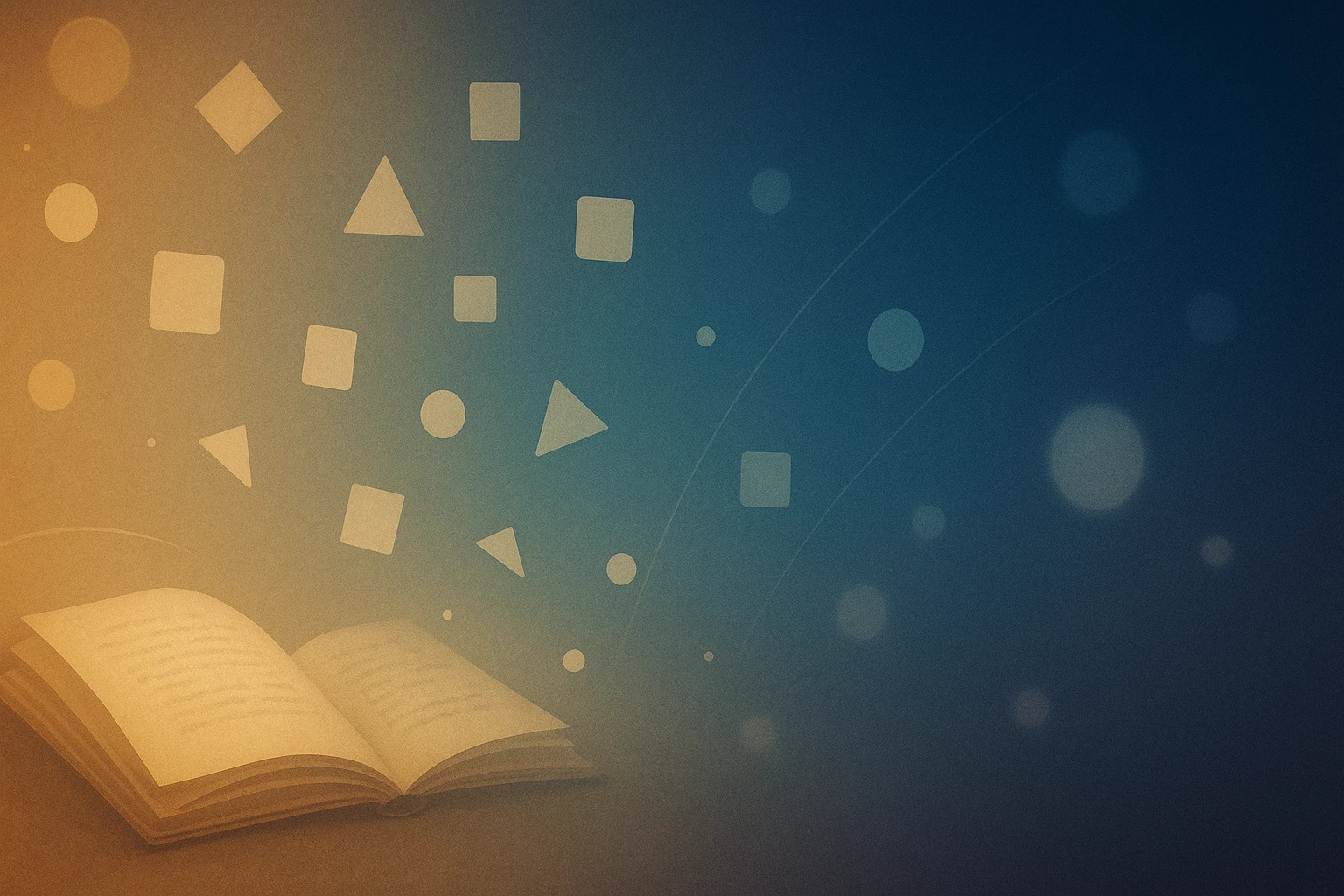何十年も前、友人に勧められて星新一氏のショートショートを文庫本で読んだことがあった。最近、岡田斗司夫氏のYoutubeチャンネルの“切り抜き”動画でも紹介されていたショートショートであり、現代のAIエージェントに関係深い内容だったので、よく知られている短編だが紹介したい。そのショートショートについてGPT 5 Thinkingに調べてもらった。
星新一氏のショートショートで、人の肩に鳥型の人工知能が止まっており、人工知能同士が会話するという未来を描いたショートショートがあったと思いますが、どのような内容であったか調べてもらえますか
GPT 5 Thinking の回答
はい、あります。作品名は「肩の上の秘書」(英題 Shoulder-Top Secretary)。星新一の短編集『ボッコちゃん』(新潮文庫 ほか)に収録されているショートショートです。(Or All the Seas With Books)
概要(あらすじ)
- 未来社会では、人々の肩にインコ型のロボット(=“秘書”)がとまっていて、持ち主が小声でつぶやく本音の短い言葉を、社交的で丁寧な建前の長い言葉に“翻訳”して相手へ伝えます。相手側のインコはそれを受け取って要点だけの短い本音に要約して主人へ返す——というインコ(AI)同士の会話で人間のコミュニケーションが進む世界が描かれます。(フィナンシャル・タイムズ)
- 物語では、営業マン(ゼーム氏)が主婦宅を訪ね、営業トークも断り文句も“インコ同士”で完結してしまい、結局は売れずに会社へ戻る……というエピソードが中心。終盤、彼はバーでひと息つき、そのひとときが「いちばんたのしい」と感じる——便利さの裏で人間が抑圧される皮肉がにじむ結びになっています。(Or All the Seas With Books)
作品のポイント
- 本音/建前の自動変換という発想で、社交と効率が極度に外部化された社会を風刺。今日の生成AIやAIエージェントへの連想でしばしば言及され、近年も英FTや各種記事で引かれています。(フィナンシャル・タイムズ)
参考(英語圏の紹介):Jay Rubin編アンソロジー評などでも“short short”の代表作として言及されています。(TLS)
本文の該当箇所のもう少し詳しい流れの要約も紹介してください
GPT 5 Thinking の回答
承知しました。星新一「肩の上の秘書」の“場面の流れ”がわかるよう、筋をもう少し丁寧に要約します。
- 近未来。人びとは肩にインコ型ロボット(秘書)を載せて暮らしている。主人のぶっきらぼうな本音のひと言を、秘書が社交的で長い建前の語りに変換して相手へ伝え、相手側の秘書はそれを要点だけの本音に圧縮して主人へ返す仕組み。本音⇄建前の相互変換で会話が進む世界だ。(The New Zealand Asian Studies Society)
- 主人公は家電会社のセールスマン・ゼーム氏。歩合を稼ごうと飛び込み営業に向かう。肩の秘書に「買えと言え」と短く命じると、秘書は流麗なセールストークを延々と展開する。(The Reading {J}ournal)
- 玄関に出てきた主婦の肩にも秘書がいる。彼女の秘書は、ゼーム側の長いトークを一言の本音(=“買え”)に要約して主婦へ伝え、主婦が「いや」と答えると、今度はそれを丁寧なお断りスピーチに変換してゼーム側へ返す。結果、インコ同士だけで応酬が完結し、取引は不成立。(一般社団法人資源循環ネットワーク)
- 会社へ戻ったゼーム氏は、成績不振で上司に叱責される。オフィスを出る前、ロッカーに自分の秘書をしまい、ひとりで退社する。(Or All the Seas With Books)
- 帰り道、ゼーム氏は行きつけのバーへ。店のマダムの肩には秘書がいるが、ゼーム氏にとってここで過ごす束の間のくつろぎが一日のいちばんの楽しみだと感じられる結び。便利な外部化が人間をどこか窮屈にするという含みを残して物語は終わる。(Or All the Seas With Books)
作品のキモは、会話の認知的負担(言い換え・察し・社交辞令)をデバイスに丸投げした社会の風刺です。秘書があるから“楽”になったはずなのに、主体性や実感が痩せていく——そんなアイロニーが、ゼーム氏の一日の流れで巧みに示されています。(The New Zealand Asian Studies Society)
さらに細部(冒頭の描写、会社シーンの調子、バーでのやりとりのニュアンス)まで掘り下げてよければ、もう少し長めの要約も作れます。
この話を何十年も前に文庫本で読んだことがあるのですが、いつごろ、出版されたものですか
GPT 5 Thinking の回答
文庫で読まれたのであれば、収録先の新潮文庫『ボッコちゃん』の初版は1971年(昭和46年)5月27日発売です。同文庫に「肩の上の秘書」が収められています。(新潮社)
※ 作品自体の初出(雑誌掲載年)については公式の網羅リストでも断片的で、確定情報を示す一次ソースが見つかりにくいのですが、英語圏の紹介などでは1961年ごろの作とされています。文庫で読む場合は上記1971年文庫初版が基準と考えて差し支えありません。(The Reading {J}ournal)
「肩の上の秘書」の内容が、Apple Intelligenceのライブ翻訳などで実現される未来(AIエージェント同士の応酬で対話が完結する未来?)に酷似しているように思われ、約半世紀前のショートショートの未来予測が的確であったことに驚いた。その証拠に、近年、各種記事でも紹介されているとのこと。将来、AIシステム(AIエージェント)により翻訳要領が調整できるようになれば、あらかじめどのような口調で相手に伝えて欲しいかをAIエージェントに教えておけば(あるいはパーソナライズされれば)、同様のことが起こり得る。
また、自身のうろ覚えの記憶とは結構違っており、あらためて話のあらすじを教えてもらうと新鮮な驚きを感じる。読んだ当時(小学生の頃)は、「便利な外部化が人間をどこか窮屈にする」とか、「主体性や実感が痩せていく」とか感じるわけもなく、ただ皮肉めいたストーリーと表現に引かれていた。主体性や実感が痩せていくのだろうか。
また、さらにパーソナライズがすすめば、忠実に外国語を翻訳するだけでなく、初対面の人、目上の人、友人、親戚、ショップの人など、相手や、相手との関係性に応じて、広義の翻訳文をAIエージェントが作ってくれるかもしれない。