下記記事で、CodexとGitHubとの連携環境について紹介したが、本記事では、Web版のChatGPTで、CodexとGitHubの連携環境を構築する手順を簡単に説明する。

(注)本記事の内容は正確性を保証するものではない。
手順1:Codex画面で「環境を選択」をクリックし「環境を作成する」をクリック
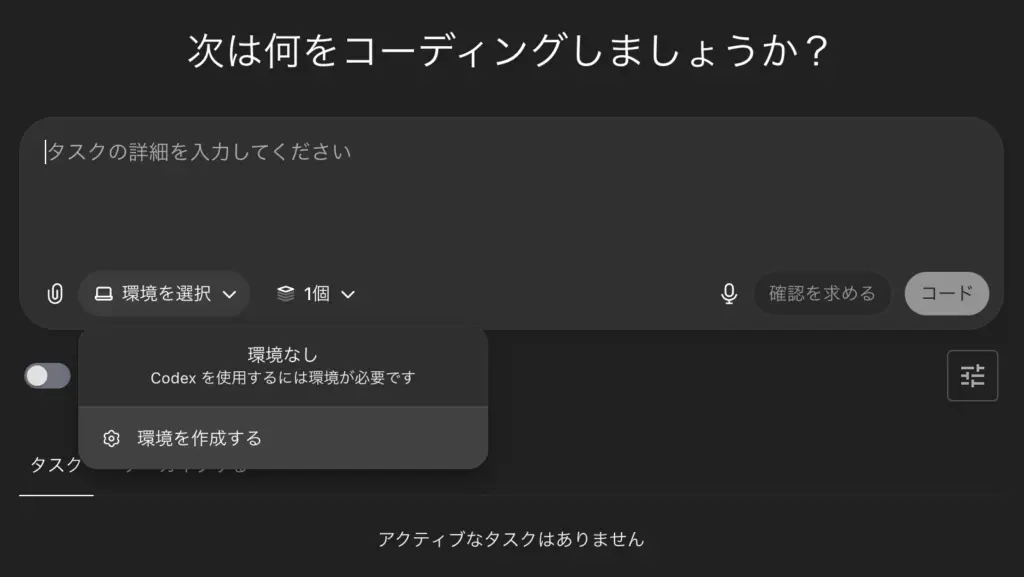
手順2:「最初の環境を作成する」という画面(下図)が表示され、リポジトリを作成していれば、候補となるリポジトリが表示されるので、連携するリポジトリをクリック
(注)連携するリポジトリをクリックして選択しないと「環境を作成する」をクリックできない。
(追記)リポジトリが表示されていない場合は、下図の「リポジトリアクセスを構成してください」を参照ください。解決しない場合は本記事の最後の「リポジトリが表示されていない場合」も参照ください。
手順3:エージェントのインターネットアクセスの有効・無効を選択する
・インターネットアクセスが無効で良ければ、「環境を作成する」をクリック
・インターネットアクセスを有効にすると、手順4の画面になる
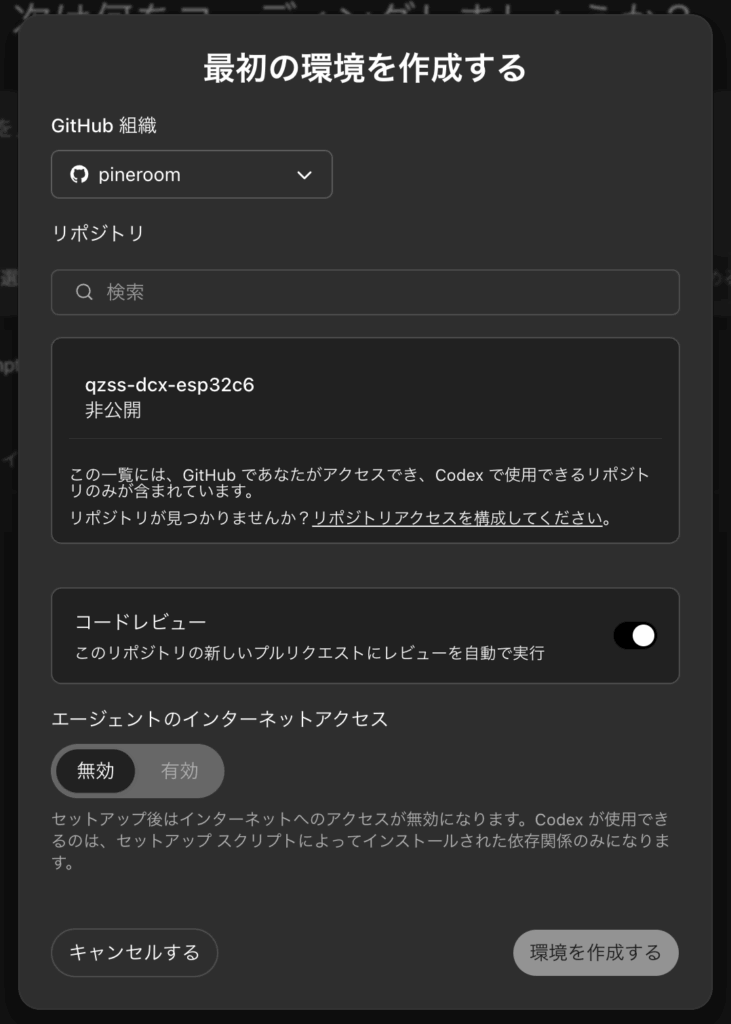
手順4:インターネットアクセスを有効にした場合の設定画面で各項目を設定
・ドメイン許可リスト:アクセスが許可されるドメインがデフォルトのものでよければ「共通の依存関係」を選択。
他に、「なし」、「すべて(無制限)」が選択できる。
・ここでは、「許可対象の追加ドメイン」と「許可されているHTTPメソッド」は下図のままとして進める
・「環境を作成する」をクリック
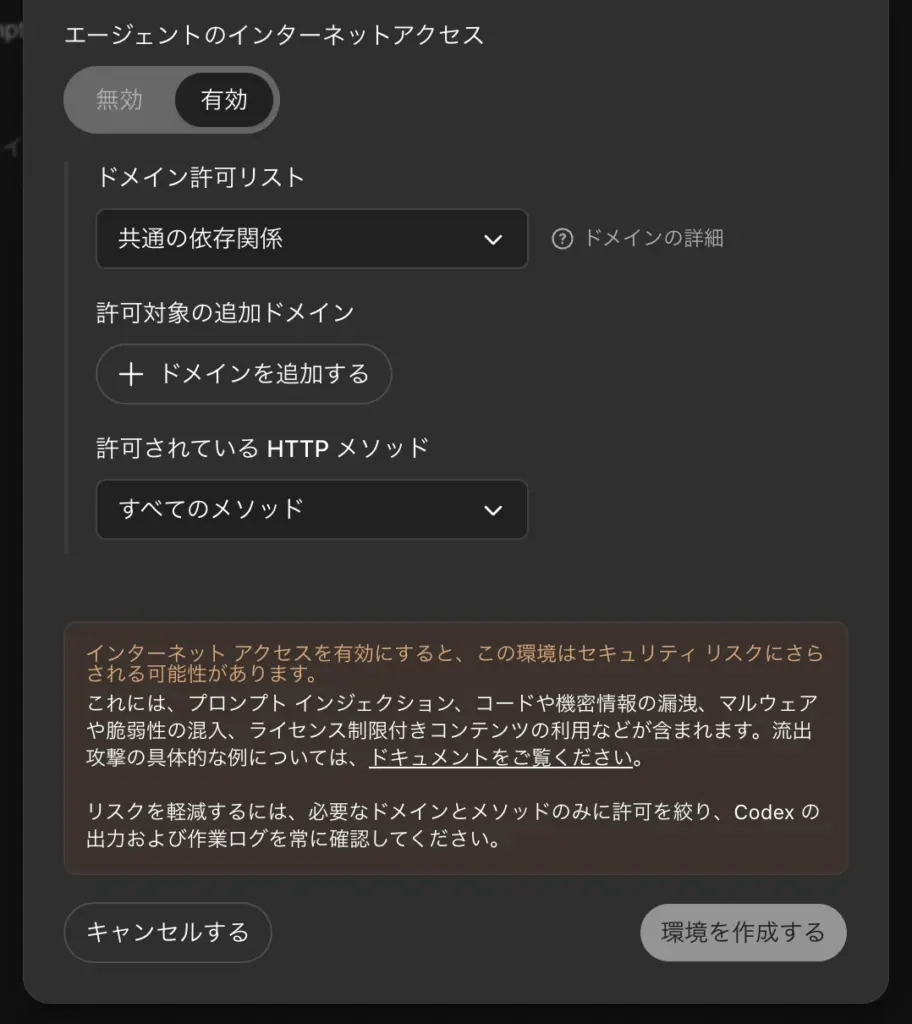
「共通の依存関係」を選択した場合に適用されるホワイトリスト(抜粋)
(このリストは「ドメインの詳細」のリンク先ページに記載されている)
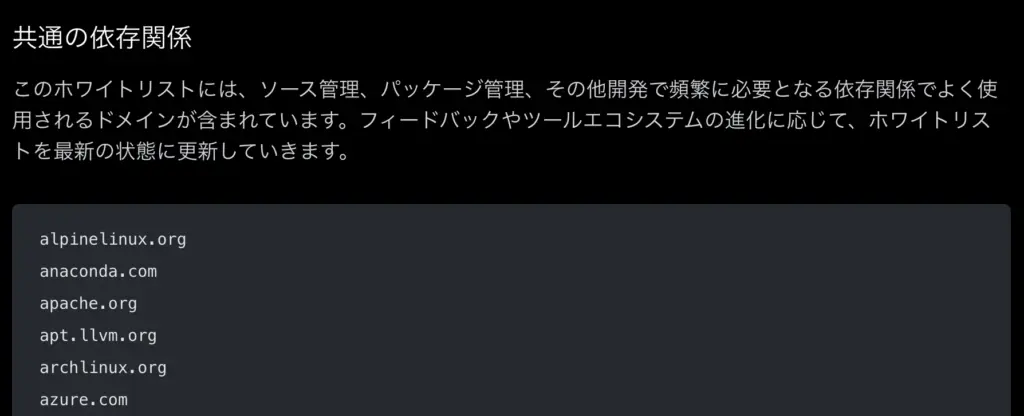
次は、作成した環境の設定を変更する場合について説明する。
まず、環境の選択メニューをクリックし、「環境を管理する」をクリック
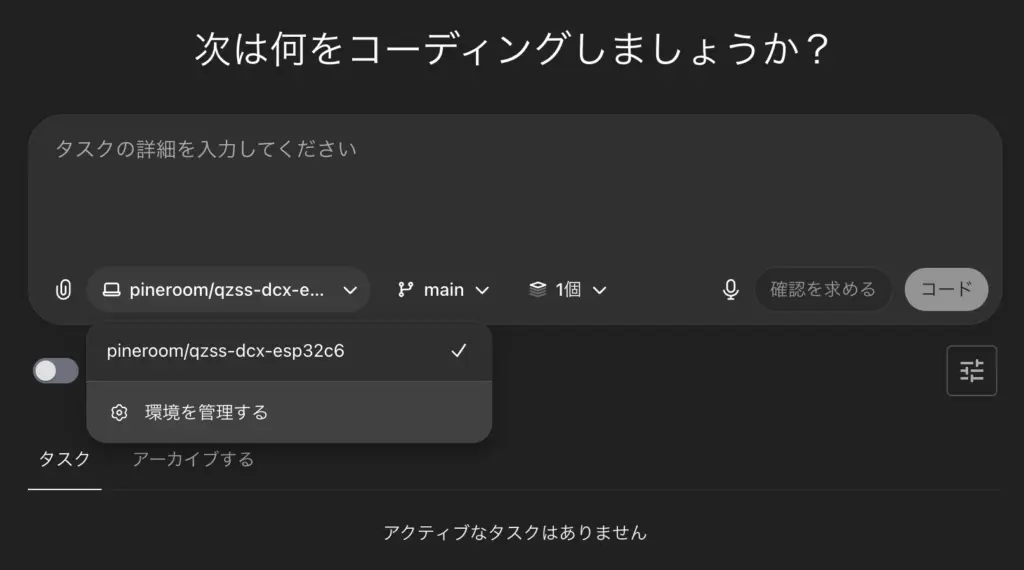
リポジトリの一覧画面が表示されるので、対象のリポジトリの「名前」をクリック
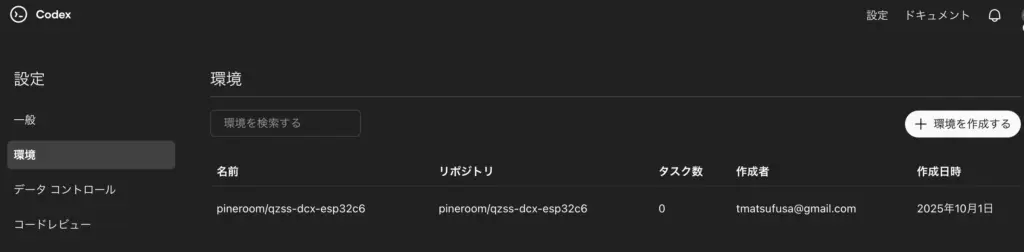
リポジトリの設定一覧画面が表示されるので右上の「編集」をクリック
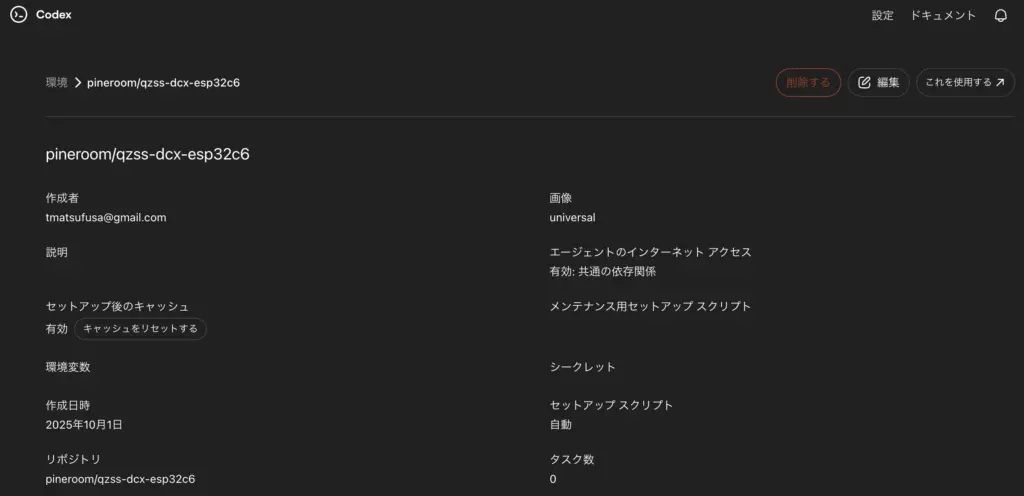
編集画面が表示される。修正後は「環境を保存する」をクリック
編集画面の各項目についてGPT 5 Thinkingに質問した。
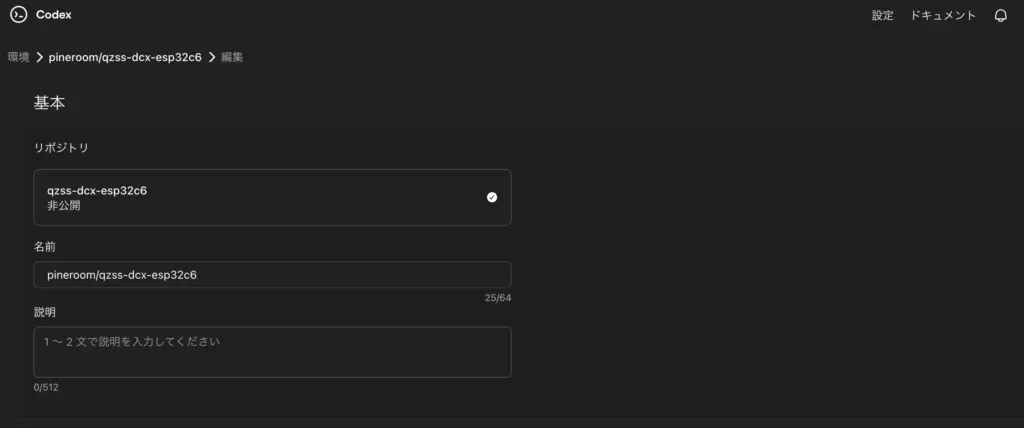
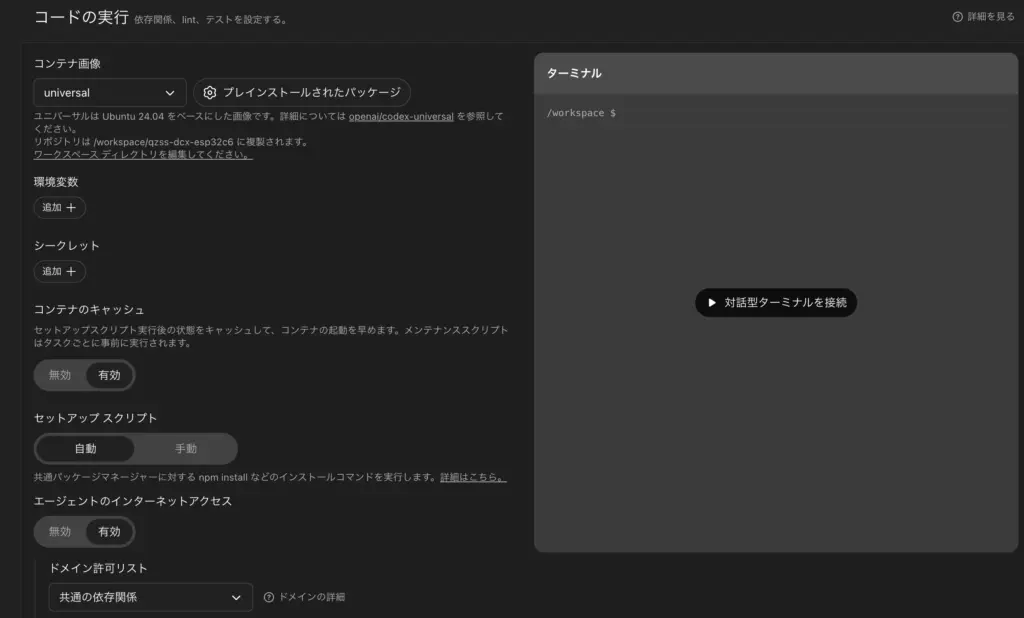
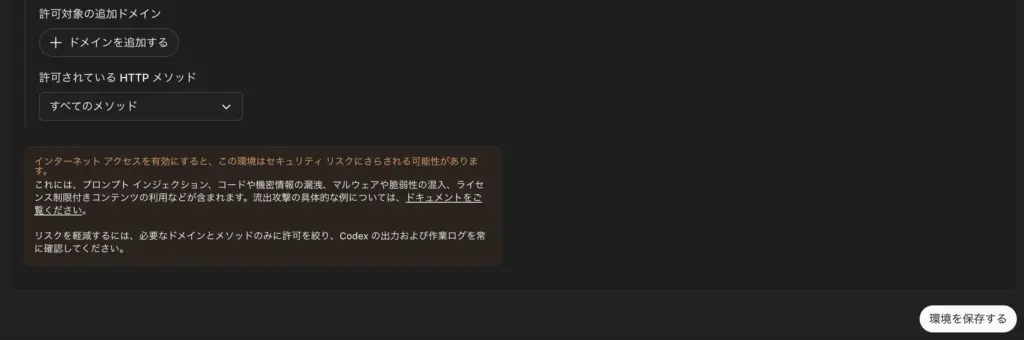
添付画像(上図)は、Codex環境の設定の編集画面です。
それぞれの項目について説明してください
GPT 5 Thinking の回答
了解です。添付画面(「基本」「コードの実行」)で見えている各項目を、上から順にわかりやすく説明します。
基本
- GitHub 組織
- Codex からアクセスを許可した GitHub アカウント/Organization を選びます。
ここで選んだ組織配下の“アクセス許可済み”リポジトリだけが次のリストに出ます。 - 目的:どのアカウントのリポジトリを使うかを切り替えるため。
- Codex からアクセスを許可した GitHub アカウント/Organization を選びます。
- リポジトリ(検索欄+一覧)
- 選択した組織内で、Codex が権限を持っているリポジトリだけが表示されます。検索ボックスで絞り込みも可能。
- 「リポジトリアクセスを構成してください」リンクは、GitHub 側で追加のリポジトリにアクセス権を与える設定(Permissions/Repository access)へ誘導するためのものです。
- 目的:この環境が“コードのソース”として参照・操作するリポジトリを決める。
- 名前
- この Codex 環境の表示名。後から一覧で識別しやすくするためのラベル(64 文字まで)。
- 例:「qzss-dcx 実験用」「blog-builder-prod」など。
- 説明
- 環境の用途メモ(512 文字まで)。利用目的や注意点、主要ツール等を書いておくと運用がラクです。
コードの実行(依存関係、lint、テストの設定)
- コンテナ画像(例:universal)
- ベースとなる実行用コンテナイメージを選びます。
universalは Ubuntu 24.04 ベースで、多言語開発を想定した汎用スタック。 - 目的:実行 OS とあらかじめ入っている基本ツールを決める。
- ベースとなる実行用コンテナイメージを選びます。
- プリインストールされたパッケージ
- ベース画像に予めバンドルされている共通パッケージ群の利用可否。
オンにすると、よく使うビルドツールや言語ランタイムのセットアップが短時間で済みます。 - 追加の依存は後述の「セットアップスクリプト」で入れます。
- ベース画像に予めバンドルされている共通パッケージ群の利用可否。
- 環境変数(追加+)
- ビルド/実行時に参照させる一般的な環境変数(例:
NODE_ENV=production、PYTHONUNBUFFERED=1)。 - 機微情報には使わず、後述の「シークレット」を使うのが原則。
- ビルド/実行時に参照させる一般的な環境変数(例:
- シークレット(追加+)
- トークンやパスワード等の機微情報を安全に注入します(ログや成果物に出ない扱い)。
- 例:
GH_TOKEN、OPENAI_API_KEY、AWS_ACCESS_KEY_IDなど。
- コンテナのキャッシュ(無効/有効)
- セットアップ後の状態をキャッシュし、次回以降の起動を高速化します。
- 依存関係を頻繁に変える開発初期は無効でもよいですが、安定してきたら有効化が時短になります。
- 依存を大きく更新したのに反映されない場合は、キャッシュを無効にするか、再作成してリフレッシュします。
- セットアップスクリプト(自動/手動)
- “環境起動直後に走る初期化フェーズ”の扱いを決めます。
- 自動:プロジェクトの種類に応じて
npm install/pip install -r requirements.txt/poetry installなど、一般的なインストールコマンドを自動推定・実行。 - 手動:自分で明示的なセットアップ手順を書きます(例:
apt-get update && apt-get install ...、npm ci、make setupなど)。 - 目的:依存の導入やビルド前準備を再現可能にすること。
- “環境起動直後に走る初期化フェーズ”の扱いを決めます。
- エージェントのインターネットアクセス(無効/有効)
- セットアップ後、エージェント(タスク実行時)が外部ネットワークへアクセスできるかの制御。
- セキュリティ重視・再現性重視なら無効(ローカル資源とロックされた依存だけで動作)。
外部 API 叩きやパッケージ取得が必要なら有効。 - メモ:多くのケースでは「セットアップ時だけネット可、実行時はオフ」にすると安全性と安定性のバランスが良いです。
- ターミナル/対話型ターミナルを接続
- 右側のパネルは環境コンテナに対するシェル操作エリア。
接続すると/workspace配下(リポジトリがマウントされる場所)で手動コマンドを試せます。 - ビルド失敗の原因調査、入っているツールの確認、手動デバッグに便利。
- 右側のパネルは環境コンテナに対するシェル操作エリア。
- ワークスペースディレクトリを編集
- リポジトリをどこにマウントするか、ワークスペースのルートを微調整したいときに使います。
(モノレポでサブディレクトリを作業ルートにする等)。
- リポジトリをどこにマウントするか、ワークスペースのルートを微調整したいときに使います。
実践的な設定アドバイス
- 権限でつまずきやすい点
リポジトリが一覧に出ない → GitHub の「Repository access」で当該リポジトリを Explicit access に追加する(組織全体許可にしていない場合)。
Private リポジトリは特に忘れがち。 - Secrets の徹底
API キーやトークンは必ず「シークレット」に入れ、環境変数に平文で置かない。 - キャッシュ運用
lockfile(package-lock.json/poetry.lock/requirements.txt等)を更新したら、一度キャッシュ無効で再セットアップ→その後に再び有効化、が安定。 - ネットアクセスの方針
①セットアップで依存取得 → ②実行時はネット遮断、が再現性・安全性◎。外部 API を叩くジョブだけ個別に有効化する。
必要なら、あなたのプロジェクト(例:qzss-dcx-esp32c6)向けに「おすすめ初期設定テンプレート(環境変数/シークレット名の例、セットアップコマンド例)」も作ります。気軽に言ってください。
「コードの実行(依存関係、lint、テストの設定)」で、「依存関係」、「Lint」、「テストの設定」について、各設定項目はどのように関係しているのですか。簡単に教えてください。
GPT 5 Thinking の回答
了解です。要点だけサクッと👇
何が「Lint」「テスト」に効くのか(対応づけ)
- コンテナ画像 / プリインストール
ここで決めたOS・言語ランタイム・ツール群が、使えるリンター/テストランナーの土台になります。
例:Node系ならeslint/vitest、Python系ならruff/pytestを動かせるかがここで決まる。 - セットアップスクリプト(自動/手動)
Lint/テストに必要な依存のインストール手順を実行します。
例:npm ci、pip install -r requirements-dev.txt、poetry install。
→ これが終わって初めてeslint .やpytestが実行可能。 - 環境変数
Lint はほぼ影響なし(たまに設定を切り替える程度)。
テストは挙動を分けるフラグでよく使います(ENV=ci、DJANGO_SETTINGS_MODULE、FEATURE_X=0など)。 - シークレット
Lint では基本不要。
テストでは統合テストで外部APIモック用のキーや、CI用トークンが必要になることあり(なるべくモック推奨)。 - コンテナのキャッシュ
依存が変わらなければlint/テストの起動が高速化。
依存更新で不整合が出たら一度オフにして再セットアップ。 - エージェントのインターネットアクセス
オフでもLintや単体テストはだいたい動く(ローカル依存のみ)。
外部APIやパッケージ取得を含む統合テストはオンが必要。
原則:セットアップではオン、実行はオフ(モック重視)が安全。 - ワークスペース / ターミナル
Lint/テストが走る作業ディレクトリ。
ターミナルは失敗時の手動デバッグに使う。
全体像(1本の流れ)
- コンテナ決定 → 2) 依存インストール(セットアップ) → 3) Lint(静的チェック) → 4) テスト(単体→結合)
この順に、上の各設定が“使えるツール・入れる依存・ネット可否・速度”を左右します。
迷ったら
- Lint/単体テスト中心:ネットオフ、キャッシュ有効
- 外部連携の統合テストあり:セットアップ時オン、実行は極力オフ+モック(例外ケースのみオン)
もっと具体的に、あなたのリポジトリ(言語/フレームワーク)向けに「おすすめ Lint & テスト最小セット(セットアップコマンドと実行コマンド)」を出すこともできます。言語を教えてください。
不明点も多いが、基本的な最小限の設定は行えた。
以降、Codexの設定画面(下図)の他の項目(一般、データ コントロール、コードレビュー)についてGPT 5 Thinkingに確認した内容を紹介する。
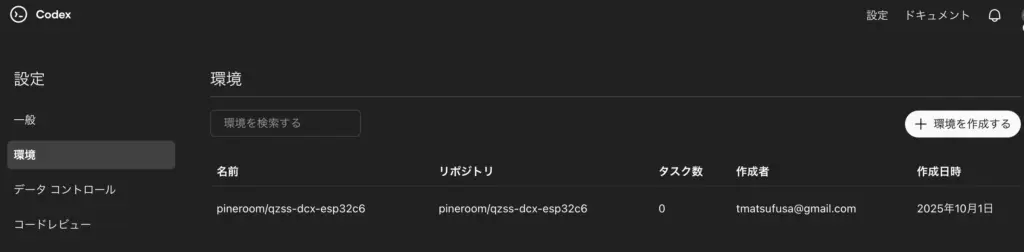
了解です。画像に写っている3つの設定タブごとに、主要な項目をサクッと解説します。
一般
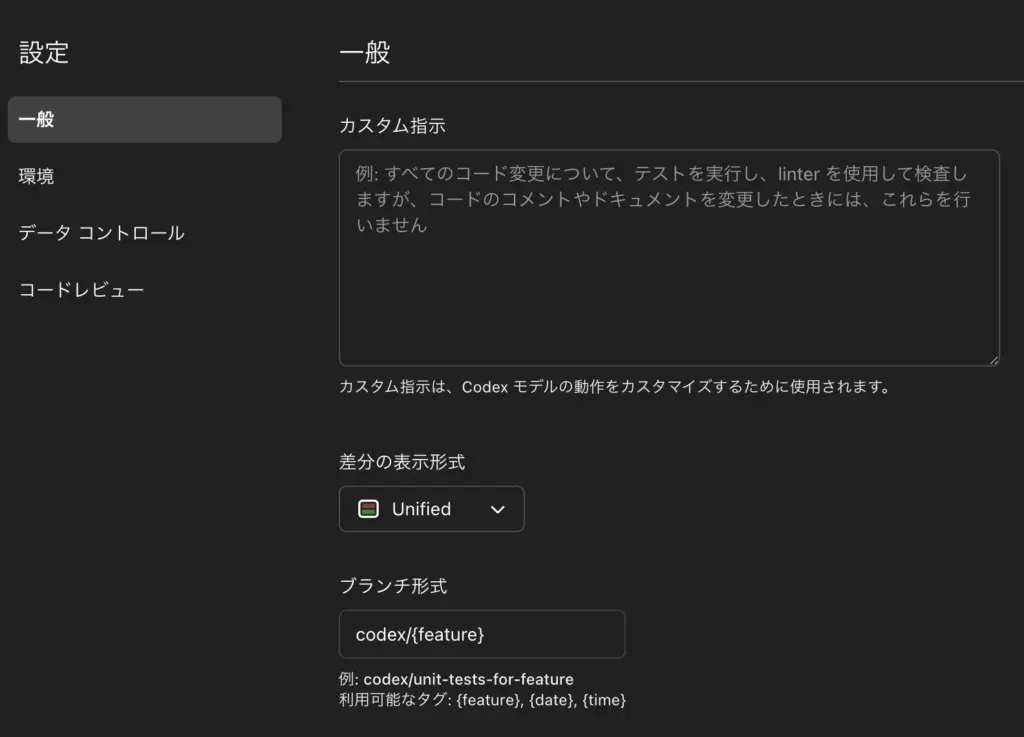
- カスタム指示
Codexに“普段どう振る舞うか”を伝える欄。例のように- すべてのコード変更では「テスト実行+Lintで検査」
- コメントやドキュメントだけの変更ではそれらを省略
…などの運用ルールを書いておくと、提案や自動アクションの基準になります。
- 差分の表示形式(Unified / Split)
プルリク等の差分の見せ方を選択。- Unified: 1列で前後の変更をまとめて表示(コンパクト)。
- Split: 左右2列で旧/新を並べる(詳細比較に向く)。
- ブランチ形式(例:
codex/{feature})
Codexが作業ブランチを切る際の命名テンプレート。{feature}・{date}・{time}などのタグを差し込めます(例:codex/unit-tests-for-feature)。
共同開発時のブランチ規約をここで統一できます。
データ コントロール
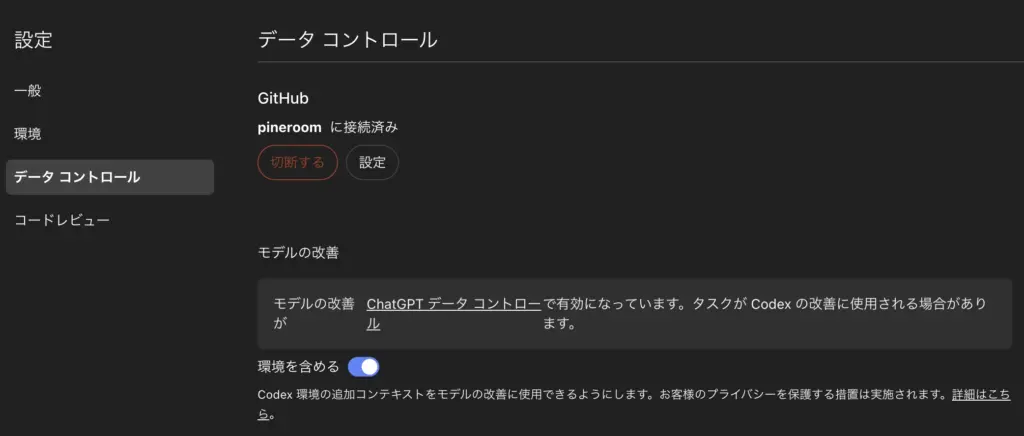
- GitHub(接続済み/切断・設定)
CodexとGitHubアカウントの連携状態。- 設定: 対象組織・リポジトリ、権限のスコープを調整。
- 切断: 連携を解除。
- モデルの改善(ChatGPT データ コントロール)
あなたの利用データを“製品改善(学習)”に使って良いかの全体設定。ここはChatGPT側のデータコントロールに準拠します。 - 環境を含める(トグル)
上記“モデルの改善”を許可している場合に、Codex環境の追加コンテキスト(依存関係・実行ログ・補助メタ情報など)も改善用途に含めるかを個別に指定。
オフにすると、環境コンテキストは改善に使われません(プライバシー重視)。
コードレビュー
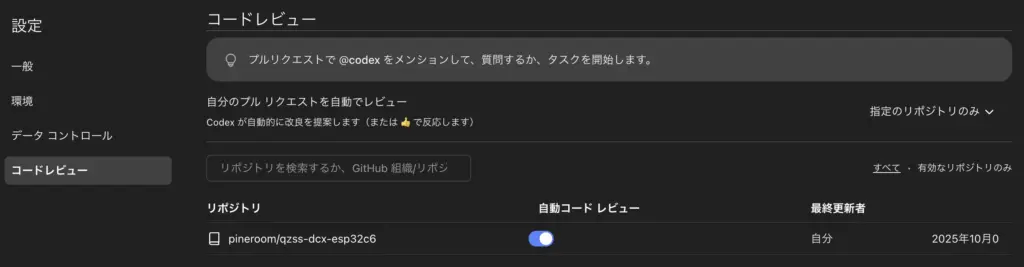
- @codex メンション説明
プルリクのスレッドで@codexを呼ぶと、質問に答えたり、リクエストを受けてレビュー/タスクを開始します。 - 自分のプルリクエストを自動でレビュー(トグル)
有効にすると、あなたが作成したPRにCodexが自動で改善提案コメントや👍リアクションを付けます。細かな指摘や修正案が自動で届きます。 - リポジトリの対象範囲
- 検索ボックス: 対象にしたいGitHub組織/リポジトリを検索して追加。
- 指定のリポジトリのみ: 自動レビューの対象を限定。
- 各リポジトリ行の自動コードレビュー(トグル)で、個別にオン/オフ。
- 最終更新者/最終更新日: 設定を最後に変えたユーザーと日時の記録。
(補足)
「リポジトリが表示されていない場合」
まず、下記記事の最後に記載の通り、GitHubアカウントの本人確認(ユーザー名の確認)や、どのリポジトリにアクセスできるかの確認を行ってGitHub側の設定を行ってください。それでも解決しない場合は、下記の質疑応答を参照してください。
添付画像は、CodexでGitHubと連携する環境を構築するための設定画面ですが、この画面にリポジトリが表示されない場合、GitHubのコネクターが設定されていないということでしょうか
GPT 5 Thinking の回答
いい質問です。
結論:リポジトリが出てこない=必ずしも「コネクター未設定」ではありません。 コネクター(GitHub連携)が入っていても、権限や対象範囲の設定で“表示ゼロ”になることがよくあります。
まず押さえるポイント
- 画面のドロップダウンで組織(Org)を正しく選択していない
- GitHub側で「特定のリポジトリのみ」許可にしていて、1件も選んでいない
- 組織の管理者承認/SSO承認が未完了(Pending)
- プライベートリポジトリの権限が付いていない
- 別の所有者(個人アカウント vs 組織)のリポジトリを見に来ている
- リポジトリがアーカイブ/非表示フィルタに引っかかっている
- 単純に再同期が未実行(キャッシュ)
すぐできる切り分け手順(おすすめ)
- 画面上部の「GitHub 組織」で目的の組織/個人を選び直す。
- 下部のリンク(画像の文言だと「リポジトリアクセスを構成してください」)をクリックして、GitHub側の連携設定へ。
- GitHub側で以下を確認:
- アプリ/コネクターがインストール済み(対象の組織に)
- アクセス範囲:
- テストとして一旦 “All repositories(全リポジトリ)” を選択 → 保存
- もしセキュリティ方針で「Selected repositories」のみなら、表示したいリポジトリを必ず追加 → 保存
- プライベートリポジトリへの読み取り権限が付与されている
- 組織のOwnerが承認している/SSOのAuthorizeが済んでいる(必要な場合)
- Codexの画面に戻り、更新(リロード)、または再同期。検索欄をクリアして全件が見える状態に。
- それでも出ない場合:
- 連携を一度Revoke(取り消し)→ 再接続
- 目的のリポジトリがその組織配下か(個人配下だった、Orgが違った等)を再確認
- テスト用にパブリックのダミーrepoを1つ作成して表示されるか確認(表示されれば権限/可視性の問題)
よくある落とし穴
- Org側の「Install App but Pending Approval」状態のまま
- Selected repositoriesに追加したつもりが保存していない
- Fork/Archiveを非表示にするフィルタが効いている
- 以前Agentモードでのみ接続しており、通常モードのCodex環境側で再認可していない
要点まとめ
- 表示が空でも、コネクター未設定と断定は不可。
- まずはGitHub側で“どの組織に・どのリポジトリに権限が出ているか”を確認し、範囲(All/Selected)と承認を整え、Codexで再同期してください。

